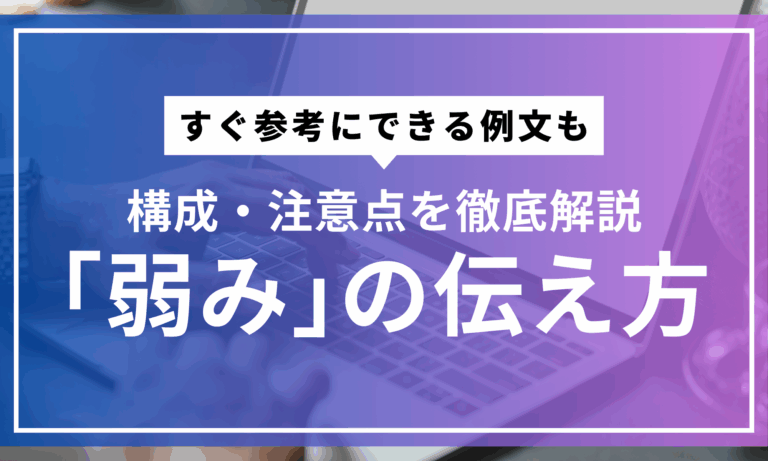はじめに|就活における「弱み」とは?企業が聞く理由
就活の面接やエントリーシートで「あなたの弱みを教えてください」と聞かれると、答えに詰まってしまう方は少なくありません。「ネガティブに受け取られてしまうのでは」と不安になり、そもそもどこまで正直に話してよいのか分からない人も多いのではないでしょうか。
強みやガクチカに比べて、弱みは答え方の正解が見えにくく、「何をどう答えればいいか分からない」といった悩みに直結しやすいテーマです。中には、弱みそのものが思いつかず、回答をつくる手前で立ち止まってしまう人もいます。
しかし実際には、「弱みをどう伝えるか」は企業が重視している評価項目のひとつです。面接官はただ欠点を聞きたいのではなく、自己理解・成長意欲・職務適性など、さまざまな観点を見ています。
本記事では就活で表現する弱みの見つけ方や伝え方に加え、気を付けるべきポイントやその対処法を例文付きで解説していきます。
そもそも「弱み」って何?伝え方の前に知っておきたい考え方
就活の場面で聞かれる「弱み」は、単なるマイナスポイントとは意味合いが少し異なります。
面接官が見ているのはマイナスな特性そのものではなく「この人は自分の傾向をどう理解し、どんな行動で乗り越えようとしているのか」という課題との向き合い方です。たとえば「優柔不断」と一言で言っても、それに悩みながら意思決定の工夫をしてきた人と、無自覚に放置してきた人とでは、受け取られ方はまったく違います。
つまり、就活で伝える「弱み」とは単なる欠点ではなく、自分の課題と成長のストーリーを伝えるための出発点だと捉えるとよいでしょう。
面接官が弱みを聞く理由
就活の面接官は「あなたの弱みを教えてください」という質問を通して、単なる欠点を知ろうとしているわけではありません。この質問で見ているのは、自己理解の深さや課題に向き合う姿勢です。具体的には、面接官は以下の4つの観点を確認するために「弱み」を聞いていることが多いです。。
自己認知の確認
弱みを通じて確認しているポイントのひとつは、「自分の傾向や課題をきちんと理解できているか」という点です。どんなに優秀な人でも弱みがない人はいません。就活ではむしろ、自分の弱みに気づき、それにどう向き合ってきたかを語れる人のほうが、信頼感や誠実さを感じさせることができます。
企業とのマッチ度の確認
企業によって求める人物像は異なります。そのため、弱みの内容を通して「この人の特性は自社の業務やカルチャーと合っているか」をチェックしています。もちろん、完璧にマッチしている必要はありませんが、面接官は「大きくズレていないか」「適応できそうか」といった点を見ています。
成長性の確認
弱みは変化の余地でもあります。面接官は「この人は過去の課題に対してどんな努力をしてきたのか」「その課題を改善する姿勢があるのか」を確認しています。つまり、就活生にとっては「弱み」の質問は単なる減点要素ではなく、成長性をアピールするチャンスでもあるということです。
業務への影響の把握
最後に、面接官は弱みが「業務にどの程度影響しそうか」も冷静に評価しています。たとえば総合商社のような顧客との商談が多い業界で就活生が「人と話すのが極端に苦手」という弱みを伝えた場合、業務上の支障が懸念されるかもしれません。一方で、弱みがあっても工夫によって改善に取り組んでいる様子が伝われば、「実践力がある」と評価することもできます。
「弱み」の見つけ方|自己分析で導く3ステップ
「自分の弱みが分からない」「強みは言えるけど、弱みとなるとピンとこない」といった声が多くの就活生から聞かれます。自分の弱みはあまり言語化してこなかった性質であることが多いので、いきなり思い浮かばなくても心配いりません。
ここでは、誰でも簡単に取り組める3ステップで弱みを導き出す方法を紹介します。
STEP1: 過去の失敗体験を整理する
まずは「うまくいかなかった経験」を思い出してみましょう。自信を持って語れる成功体験よりも、「思うようにいかなかった」「あとから反省した」といった場面のほうがヒントになります。
たとえば、「サークルでイベントの準備を任された際、作業が遅れて直前までバタついてしまった」「学園祭の企画で複数の案から選べず、決定が遅れてしまった」「バイトで改善策を思いついたが、自信がなくて言い出せずに終わってしまった」といった経験は弱みを見つける手がかりになります。
STEP2: 原因となる行動・傾向を抽出する
STEP1で挙げた失敗体験をもとに、「なぜそうなったのか?」を深掘りしてみましょう。大切なのは失敗そのものではなく、自分が繰り返しやすい行動パターンや思考の癖を見つけることです。
たとえば、「イベント準備が直前まで終わらなかった」という場合は、「納得いくまで手を加えたい」「細部の完成度を重視する」といった完璧主義の傾向があるのかもしれません。
「企画案の決定が遅れた」という場面では、「慎重すぎてなかなか決断できない」「他人の意見を待ってしまう」といった優柔不断な側面が背景にあるのかもしれません。
また、「改善策を思いついていたのに提案できなかった」というときには、「否定されたくない」「場の空気を壊したくない」といった遠慮がちな性格が関係していることもあります。
このように、表面的な出来事にとどまらず、「なぜそうなったのか?」という視点で振り返ることで、就活で伝えられる意味のある弱みが見えてきます。
STEP3: 応募企業との接点を意識する
自分の弱みが見えてきたら、「この企業ならどう受け取るか」という視点で整理してみましょう。
たとえば、完璧主義の傾向は、丁寧な作業や品質管理が重視される職場ではプラスに働くことがありますが、スピード重視の現場では「初動が遅い」と受け取られる可能性があります。
「慎重すぎる」「決断に時間がかかる」という弱みは、ミスを避ける姿勢が求められる組織では評価されやすい一方で、変化への対応が求められる職場ではマイナスに映るかもしれません。
また、「主張が弱い」「遠慮しがち」といった性格は、縦割りの傾向が強い組織では協調性として捉えられる可能性がありますが、自己発信が求められる職場では懸念されやすい傾向があります。
このように、企業によって重視する人物像は異なります。自分の弱みがどんな職場でどう評価されるかを考えておくことで、就活での伝え方や言い換え方の方向性が見えてきます。
補足: 強みの裏返し/他己分析/診断ツールの活用
就活で示す自分の弱みがどうしても思いつかない場合は、次のようなアプローチを試してみるのもおすすめです。
たとえば、自分の強みをひとつ取り上げ、それが裏目に出たときのリスクや短所を考えてみましょう。「粘り強さ」は裏を返せば「こだわりが強く柔軟性に欠ける」、「慎重さ」は「決断が遅れる」といった具合です。この方法は、自己PRと一貫性のある弱みを示しやすいというメリットもあります。
また、自分では気づきにくい癖や傾向を他人からの視点で教えてもらうことでも、自分の弱みを知ることができます。友人や家族、自分をよく知る人などに「私のどんなところが課題だと思う?」と率直に聞いてみると、思わぬヒントが得られることがあります。
自己分析ツールや適性診断を活用して、自分の性格の傾向や行動パターンを客観的に整理することもおすすめです。「慎重すぎる」「こだわりが強い」などの性格タイプが可視化されることで、自分の弱みを言語化しやすくなることがあります。
性格タイプ別|就活で使える「弱み」の例と伝え方
これまで、自分の弱みは過去の失敗経験や行動の傾向から導かれることを見てきました。
ここでは、その応用として性格の傾向をもとにした就活での弱みの伝え方を紹介していきます。就活でマイナスに見られがちな性格も、構成や表現を工夫することで適切に伝えることができます。
この章では完璧主義・慎重・マイペース・受け身の4つの性格の傾向を取り上げます。それぞれのタイプに近い例をもとに、就活の面接やエントリーシートで使える実践的な伝え方を確認していきましょう。
完璧主義型
「納得いくまで取り組みたい」「細かい部分が気になる」といった完璧主義型の傾向は、責任感や仕事への丁寧さにつながる一方で、「初動が遅い」「融通が利かない」と見られてしまうことがあります。
就活で弱みとして扱う場合は、「こだわりすぎて失敗した経験」と「それを踏まえた改善の工夫」をセットで伝えるのがポイントです。こだわりの強さが悪いのではなく、それをどう扱えるようになったか、という変化が伝わるようにしましょう。
| 例文:私の弱みは、完璧を求めすぎて動き出しが遅れてしまうところです。大学のゼミ活動でプレゼン資料の作成を担当した際、自分が納得できる構成やデザインになるまで何度も手直しをしていたところ、メンバーへの共有が予定より遅れてしまい、全体の準備が直前になってしまいました。この経験を通じて、「完璧さよりも、早く形にして共有することの方が価値がある場面もある」と気づき、それ以降はまず7割の完成度でもよいので初稿を出して意見をもらうようにしています。今後も「納得のいくものをつくる」という姿勢は大切にしながらも、チーム全体のスケジュールや目的を意識した動き方を心がけていきたいです。 |
慎重・優柔不断型
「しっかり考えてから動きたい」「他人の意見も尊重したい」といった慎重な性格は、意思決定の質を高める強みでもあります。一方で、就活では「判断が遅い」「自信がない」と受け取られるリスクもあるため、伝え方には工夫が必要です。
就活の場面で弱みとして扱う際は、「なぜ判断に時間がかかっていたのか」といった背景を整理し、その上で「どう改善したか」「今はどう工夫しているか」を具体的に伝えるようにしましょう。
| 例文:私の弱みは、慎重になりすぎて判断に時間がかかるところです。飲食店のアルバイトでホールリーダーを任された際、新人のシフト希望がバラついていたため、誰をどの時間帯に配置すべきか悩みすぎてしまい、最終的な提出が遅れてしまったことがありました。このとき、店長から「迷ったらまず仮で組んで、相談しながら調整すればいい」とアドバイスを受け、自分ひとりで完璧に決めようとする姿勢が判断を遅らせていたことに気づきました。それ以降は、情報が揃っていなくてもまず案を出して、周囲とすり合わせながら前に進めるよう意識しています。今後も、慎重さは大切にしつつ、判断と行動のバランスを意識していきたいと考えています。 |
マイペース・協調性に課題型
「自分のペースで考えたい」「あまり周囲に流されたくない」といった姿勢は、物事にじっくり向き合える一方で、集団の中では「空気を読まない」「連携が取りにくい」と見られてしまうことがあります。
このタイプの弱みは、「場の状況を見て動くことへの意識」「周囲との連携を意識するようになった行動の変化」などを伝えることで、協調性への前向きな姿勢を示すことができます。
| 例文:私の弱みは、周囲との連携よりも自分の進め方を優先してしまう傾向があることです。学生団体でイベント運営を担当していた際、自分の作業の進め方を優先してしまい、全体の進捗確認やメンバーとの連携が後手になった結果、情報共有が不足してしまったことがありました。この経験から、「個人の作業だけで完結するものではない」「チームとして進める以上、周囲とタイミングを合わせる意識が必要だ」と実感しました。それ以降は、自分の作業計画をチーム内で先に共有したり、週に一度は全体の進捗を口頭で確認するようにするなど、他メンバーと連携を取る動き方を意識しています。今後も、個人の集中力とチーム全体への配慮の両立を心がけていきたいです。 |
主張が弱い・受け身型
「空気を乱さないようにしたい」「迷惑をかけたくない」といった気遣いの強さは、慎重さや協調性としても活かされます。しかし、就活の場面では「積極性に欠ける」「リーダーシップが弱い」といった懸念をもたれることもあるため、言い方や補足が重要です。
就活で弱みとして伝える際には、「どんな場面で受け身になったか」だけでなく、「どうすれば主体的に関われたか」を学び取った姿勢を明確にすると、ポジティブな印象につなげやすくなります。
| 例文:私の弱みは、自分の意見を後回しにしてしまいがちなところです。大学のグループワークでテーマを決める際、周囲の意見を優先するあまり、自分の考えを言わないまま進行してしまったことがありました。結果的に、あとから「もっと早く言ってくれればよかった」と言われ、自分の受け身な姿勢がかえってチームに負担をかけていたことに気づきました。この経験をきっかけに、「意見を出すことが全体のためになる場面もある」と意識するようになり、それ以降は初期段階で必ず一度は自分の考えを伝えるようにしています。今後も、相手への配慮を大切にしつつ、自分の意見も積極的に発信して、チームへの貢献度を高めていきたいです。 |
面接・ESでの「弱み」の伝え方|構成テンプレとNG例
就活において弱みを伝えるときは、単に欠点を述べるだけでは不十分です。
大切なのはどのように捉え、どう向き合ってきたのかまで含めて伝えることです。就活で評価を受けるポイントは、「自己認知の深さ」「改善に向けた具体的な行動」「成長に至るプロセスの一貫性」です。
この章では、評価されやすい伝え方の構成テンプレと、逆に評価を下げてしまいやすいNG例を紹介します。
基本の構成テンプレ(結論→具体例→改善→変化)
就活における弱みは、伝え方によって印象が大きく変わります。
単なる反省や失敗談で終わるのではなく、「成長につながる課題」として捉えることが重要です。そこで意識したいのが、「結論→具体例→改善→変化」の順で構成することです。これにより内容が整理され、読み手に伝わりやすくなります。
この構成は、エントリーシートや面接でも使える汎用的な型です。
本記事で紹介している性格タイプ別の例文も、すべてこの構成に沿ってつくられています。構成に迷ったときは、まずこの流れに当てはめてみるのがおすすめです。
【1. 結論】
「私の弱みは◯◯です」と、最初に一言で示します。
抽象語だけでなく、「どういった場面で表れやすいか」を添えると、弱みの輪郭がはっきりします。
【2. 具体例】
実際に弱みが出たエピソードを紹介します。
「何に取り組んだ際に」「どんな困りごとが生じたのか」「どんな影響があったのか」まで書くと、納得感が高まります。
【3. 改善】
その経験をふまえて、どんな工夫や行動を試みたのかを述べます。
努力や工夫が具体的であるほど、誠実さや主体性が伝わります。
【4. 変化】
改善によって、今はどう変わっているのか、何ができるようになったのかを示します。
現在進行形での成長意識が見えると、面接官からの評価にもつながります。
このテンプレを意識するだけで、自己理解や成長意欲を自然にアピールすることができます。弱みの伝え方に迷ったときはまずこの形をベースに考えてみましょう。
伝え方で評価を下げるNGパターンと対処法
就活で弱みを正直に話そうと意識していても、伝え方次第ではかえって評価を下げてしまうことがあります。特に、以下のようなパターンは面接官にネガティブな印象を与えやすいため、注意が必要です。
抽象的すぎる/具体例がない
「慎重なところが弱みです」「完璧主義な性格です」など、一言だけで終わる回答は要注意です。
どんな場面でどう困ったのかがわからないため、面接官に「本当に自分を理解できているのか?」「仕事でも同じことを繰り返すのでは?」と不安を与えてしまいます。
NG例
「私の弱みは心配性なところです。以上です。」
どんな場面でどう困ったのか、何をどう改善したのかが一切見えてきません。
改善ポイント
具体的なエピソードや経験とセットで伝えることで、「その弱みに本当に向き合ってきた」ことが伝わります。
「どんな場面で」「どう表れて」「どんな影響があったのか」を明確にしたうえで、改善や変化のエピソードにつなげましょう。
| 改善後の例: 私の弱みは、心配性なところです。アルバイトで書類作成を担当した際、提出前に何度も見直してしまい、締切直前まで時間をかけてしまいました。誤字脱字などのミスは防げたものの、業務のスピード感に課題を感じました。そのため、見直しの時間も含めて逆算し、早めに着手して余裕を持ったスケジューリングを心がけるようにしました。加えて、見直しの回数やタイミングも決めることで、区切りをつける工夫もしています。今後も、正確性を保ちながら納期を守るスケジュール管理ができるように心がけていきたいと考えています。 |
「弱み」がただの強みアピールになっている
「責任感が強すぎて抱え込みがち」「完璧主義なので妥協できない」といった、強みの裏返しのような回答は、伝え方によっては逆効果になることがあります。
一見ポジティブに見えますが、「本当に改善すべき課題として向き合っているのか」が伝わらなければ、誠実さに欠ける印象を与えてしまいます。
NG例
「私の弱みは、完璧を求めすぎるところです。ただ、それによって仕事の質は上がっていると思います。」
弱みとしての問題点や改善への努力が語られておらず、強みのアピールに終始しています。
改善ポイント
ポイントは「本人の困った経験であるかどうか」。
その弱みによって課題として感じているポイントを、具体的な経験とともに伝えられると自分の弱みへの理解度の高さを示すことができます。あくまで「強みになり得る側面もあるが、明確に改善の対象として取り組んでいる」という姿勢を伝えることが大切です。
| 改善後の例: 私の弱みは、完璧を求めすぎるところです。アルバイトで新しいメニューの作り方を覚える際、レシピの分量や手順を何度も確認してからでないと動き出せませんでした。先輩から「やりながら覚えることも大切だよ」とアドバイスを受けたことで、現場では柔軟に動くことも重要だと気づきました。それ以降はまず一度実践してみて、フィードバックを受けながら修正する姿勢を意識するようになったことで、メニューの習得速度も改善されました。今後も、スピード感を意識することを大切にしたいと考えています。 |
「ありません」と答える
「特に思い当たりません」「弱みはありません」といった回答は、もっとも避けるべきNGパターンのひとつです。
どんなに優秀な人でも、弱みがまったくない人はいません。正直に答えることを避けた姿勢や、自己分析の甘さを疑われてしまう可能性があります。
NG例
「弱みは特にないと思います。普段からあまり失敗しないので……」
自己認知の浅さや、課題に向き合う姿勢の欠如として捉えられやすいです。
改善ポイント
大きな失敗である必要はありません。「指摘されたことがある」「あとから振り返って反省した」など、小さなきっかけから振り返ってみましょう。
大切なのは弱みがあることではなく、「それに気づき、改善に取り組んでいること」を伝えることです。
身近な経験をベースに素直に語った方が、むしろ好印象です。たとえば、指示を受けるときにメモを取り忘れてしまうことを指摘された経験があるなら、それは詰めの甘さや準備不足といった弱みにもつながります。
| 改善後の例: 私の弱みは、細部の詰めが甘くなってしまうところです。以前、サークルでイベントの準備を担当した際、指示された内容をその場でメモせずに進めてしまい、細かな項目を見落として修正対応に追われることがありました。この経験から、指示を受けるときは必ず要点をメモし、タスクはToDoアプリに整理して可視化するようにしたことで、現在では事前準備や確認の精度も上がりました。今後も、細部に気を配りながら丁寧な仕事を心がけていきたいです。 |
仕事に致命的な影響がある弱みを選ぶ
業務に深刻な支障を与える可能性のある弱みを伝えると、「そもそもこの仕事に向いていないのでは?」という懸念を持たれてしまいます。
たとえば、チームでの協働や他社との連携が中心となる仕事において「人と話すのが極端に苦手」といった弱みを伝えることは、業務への支障をダイレクトに想起させるため、避けた方が良いです。
NG例
「私の弱みは、人と話すのが苦手なことです。黙々と作業するのが得意です。」 協働や連携が前提となる多くの仕事において、選考突破が難しくなる可能性があります。
改善ポイント
弱みを伝えるときは、業務に支障が出ない範囲であることと、自分自身が成長の余地を感じているものであることが重要です。
面接官に伝える際には、工夫や改善に取り組んでいるエピソードを添えることで、誠実な自己理解と成長意欲をアピールできます。
| 改善後の例: 私の弱みは、物事の優先順位をつけるのが苦手なところです。学生団体の活動で複数の業務を抱えていたとき、すべてを同時に進めようとしてしまい、結果的に重要なタスクの締切直前まで手をつけられず、チームに迷惑をかけてしまった経験があります。それ以来、タスクを洗い出して緊急度・重要度で分類し、優先順位をつけて進めるよう意識しました。日ごとの進行表もつくるなど定期的に進捗を確認し、すべきことを可視化することで、集中すべきポイントを見失わないようにしています。今後も、周囲との連携を意識しながら着実にタスクを処理できるよう工夫を続けていきたいと考えています。 |
改善意欲や変化が見られない
「◯◯が苦手です」「性格的にこうなんです」など、ただ弱みを述べるだけで終わってしまう回答は評価されません。
企業が見ているのは欠点そのものではなく、「それをどう受け止め、どう行動してきたか」です。改善への取り組みや、そこから得た学びが見えなければ、成長意欲が感じられず、マイナス評価につながる可能性があります。
NG例
「私の弱みは、優柔不断なところです。昔からそうなので、今もあまり変わっていません。」
自己認知はありますが、向き合う姿勢や改善する努力が一切語られていません。
改善ポイント
たとえ弱みがまだ完全に克服できていなくても、「だからこそ〇〇に取り組んでいる」「最近では△△という変化があった」といった改善の姿勢を見せることが大切です。
「行動→変化→今後の意識」という流れに沿って伝えることで、弱みに向き合う姿勢や改善意欲を十分に示すことができます。
まとめ|自分に合った「弱みの語り方」を見つけよう
就活における「弱み」は、伝え方ひとつで評価が分かれます。
大切なのは、「自分のどんな傾向が弱みとして表れるか」を客観的に理解し、それを納得感のある構成で伝えることです。
このような問いに向き合うこと自体が、就活を通じて求められる「自己認知力」や「成長意欲」を示すチャンスでもあります。
本質は「自己理解」と「構成力」
就活で伝える「弱み」は、ただの欠点ではありません。重要なのは、「それをどう捉え、どのように乗り越えようとしているか」です。
そのためには、自分自身の行動や傾向を言語化し、納得感のあるエピソードで構成する力が求められます。言い換えれば、「弱みを語る力」はそのままビジネスパーソンとしての基礎力にもつながるのです。
自己分析に不安がある方へ|ES添削ツールの活用も
「自分の弱みが見つからない」「どう言語化すればいいか分からない」という方は、ツールを活用してみるのもひとつの手です。
BaseMeには、自己分析診断やES添削AIなど、就活の自己理解を深めるための機能が揃っています。客観的な視点からフィードバックを得ることで、「本当に伝わる自己PR」や「説得力ある弱みの語り方」が見えてくるはずです。さらにBaseMe AIでは、自己分析だけでなく、企業研究、面接対策、グループディスカッション対策まで幅広くサポートしていますので、ぜひ活用してみてください!(ここからBaseMeを試してみる)