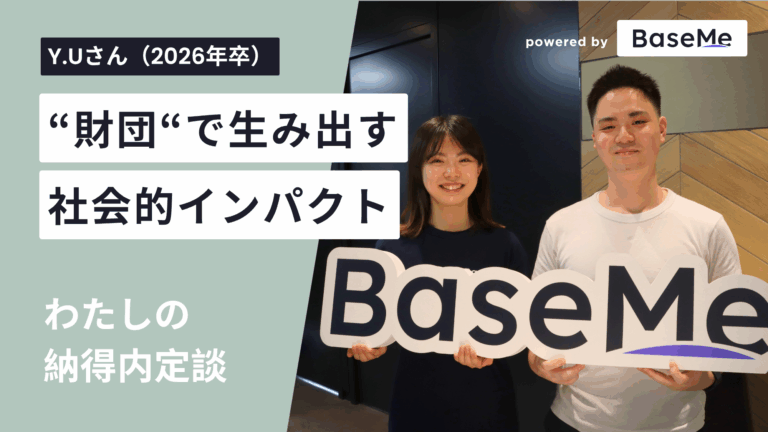要約まとめ
はじめに
「焦らない」「どうにかなる」——これは、日本財団に内定を獲得したY.Uさんの就職活動を象徴するキーワードだ。多くの就活生が熾烈な競争の中で不安を抱え、マニュアル通りの対策に追われる中、Y.Uさんは自らの価値観を軸に、独自の道を歩んできた。
「大前提として、特定の企業など“絶対ここに行きたい”という強い思いはあまりなかった」と語るY.Uさんの就活は、特定の企業や業界を目指すものではなく、その時々で「自分が何をやりたいのか」、そして「キャリアの初期にどんな経験を積めば、その後目指したい姿に近づけるか」といった視点をもとに、柔軟に考えていくプロセスだったのです。
——そのような姿勢は、一般的な就活のあり方とは異なりますね?
「就活のしきたりみたいなものに、別にテンションが上がることも、抵抗を感じることもなかったですね。」とY.Uさんは振り返る。ウェブテスト対策本は「ほぼ綺麗な状態」のまま。「ウェブテスト対策した方が、なんか選択肢が増えてたんだろうなと思いつつ。うん、まあ、なんかでも別になんかそれはチョイスじゃないですか」という言葉からは、一般的な就活プロセスを単なる選択肢と捉え、それに全面的に従う必要はないという姿勢が見て取れる。
本記事では、Y.Uさんの幼少期からの価値観形成、多様な業界での模索、そして最終的なキャリア選択に至るまでの思考プロセスを掘り下げ、現代の就活生にとって示唆に富む「型にはまらない就活」の本質に迫る。
就活スタート:迷いと模索の入り口
Y.Uさんが就職活動を本格的に意識し始めたのは、大学院への進学を決断した頃だった。
「24年の4月に大学院に入ってるんですね。23年の10月ぐらいに、その合格者向けに資料が来てて」と語るように、大学院からの案内が進路を考えるきっかけになった。
——その時点では、就職と博士課程進学の両方を検討されていたんですか?
「修士論文を書かなければならなかったので、就活をどう進めるかというよりも、博士課程に進む人は早めに進路を決めて、スケジュールが後ろ倒しにならないようにするように――ということは、研究科の先生からも言われていました。」とY.Uさんは説明する。「そのあたりから、「どういう会社に進むのか」ということに加えて、そもそも就職するのか、それとも博士課程に進学するのかといった選択肢も含めて、少しずつ考え始めていきました。」
最初に挑戦したのはコンサルティング業界だった。
「社会学研究科の多くは、最近はコンサルに進むことが多いです。なので「とりあえず、じゃあコンサルを受けてみよう」という気持ちで、大手コンサルティングファームに応募しました。
——コンサルティング業界での選考はいかがでしたか?
「エントリーシートとか、提出する書類はいろいろあったんですけど、それについては全部コンサルティングファームで働く知り合いからフィードバックをもらった上で出しました。で、まあ書類はちゃんと通ったりしていましたね。」とY.Uさんは語る。しかし、グループディスカッション(GD)の段階で違和感を覚えることになった。
「グループディスカッションをしていると、すごく嫌な感じの学生に出会うことがあって。たぶん、それが本心というよりは、プレッシャーのかかる場面でそういう態度が出てしまっているんだとは思うんですけど……」
そんな経験から、「そういう人が集まる母集団がいる会社や業界は、自分には向いていないかもしれない」と感じ、「撤退する」判断をしたという。
このように、Y.Uさんの就活は最初から自分の価値観と周囲の環境との相性を重視するものだった。「お互いのためにはい、違うんだろうな」という言葉からは、企業文化との相性を冷静に見極める姿勢が垣間見える。
秋冬:多様な業界との出会いと自己理解の深化
夏のコンサル業界での経験を経て、秋冬にかけてY.Uさんはメディア業界に目を向けた。
「マスコミを志望された経緯や、関連するご経験などはありますか?」という質問に対し、Y.Uさんはこう答えた。
「まさにその僕が、大学3年の頃から、ビジネスメディアのPIVOTに関わっていて……」
——PIVOTでの経験が、メディアへの関心につながったんですね。
「ずっとメディアには関心があったんです。つまり、マスメディアという“マス”に対して情報を伝達する仕組みを通じて、社会に何らかの変化を起こすことが本当に可能なのか。そういった問いを、個人的なクエスチョンとしてずっと持っていました。」とY.Uさんは語る。
その後、彼は「ある地上波テレビ局に籍を移し」し、「その流れで、正社員として、マスコミやメディアに関わること、あるいは記者職に近い形で関わることにも関心を持つようになった」と語る。
そして、「新聞社やテレビ局にエントリーしていた」という。
しかし、新聞社でのインターン経験を通じて、「めちゃくちゃ外部の変化に鈍い」という組織の体質に疑問を持つようになった。「なんというか、余計なノイズが入るとすぐに判断が鈍るような会社、という印象を受けたんです。そういう意味で、“どうせ自分とは合わないな”と感じるようになりました。」同時期に、Y.UさんはVC(ベンチャーキャピタル)業界にも目を向けた。
——VCに興味を持たれたのはなぜですか?
「広く言えば“秋冬選考”という括りで、いろんな企業を同時並行で、だいたい同じようなタイミングで受けていました」とY.Uさんは説明する。
「何かしら社会にインパクトを与える仕事がしたいという思いがあるんです。メディアというのは、ある種、社会課題を世論のアジェンダに載せることで、間接的に社会にインパクトを与えている。その点に魅力を感じていました。」
VCについては、「VCについても、基本的に僕は“良い資本市場をつくりたい”という思いをずっと持っていて、それは今でも変わっていません。」。
しかし、面接の中で「倫理的な」話をすると、「うちはでも結局利益出さないと会社として成り立たないから、いや、そういうことじゃないよ」と言われ、「おっしゃる通りですね」と応じる形となった。
特に印象的だったのは、Y.UさんがPIVOTでの経験を通じて得た気づきだ。「再生数のミッションを持ってなかった」という環境で、「とにかくいいコンテンツを作れ」というミッションを持って活動していたという。「就活で説明する時に逆に大変だった」と語るように、数値目標ではなく質を重視する姿勢は、一般的な就活の文脈では説明しづらいものだった。
このように、Y.Uさんは秋冬にかけて多様な業界との出会いを通じて、自己理解を深めていった。それは「社会にインパクトを与えたい」という一貫した想いと、各業界の現実とのギャップを見極める過程でもあった。
就活の軸と価値観:公共性と市場性の交差点で
Y.Uさんのキャリア観の根底には、幼少期から培われてきた「社会」や「公共」への強い意識がある。その原点は、国立の付属学校での経験にさかのぼる。
Y.Uさんは、幼稚園から中学校まで国立の附属校に通っていたという。小学生の頃には、通学中に見知らぬ大人から「お前なんか、国の税金で大学が作った学校に来やがって」などと、罵声を浴びせられた経験もあった。。
——それはどのような状況だったのでしょうか?
「近くに場外馬券売場があったんですけど、たぶん競馬で負けた帰りの人とかに、『お前、国の金でそんな学校に通って、なんなんだ』みたいなことを、けっこう言われてたんですよ。小学生の頃は制服も着ていたので、目立ったのかもしれません」とY.Uさんは振り返る。
また学校でも、「お前たちは将来的に国のエリートになるんだから」といったことを、ある種“刷り込まれる”ように言われていたという。
こうした経験が、「何かしら社会にインパクトを与える、貢献できる仕事をしたい」というY.Uさんの思いの土台になっていった。
「個人的に、自分だけが勝つようなゲームには本当に興味がない。というか、そもそもそういうことができないんです」
——「できない」というのは?
「無理ですね。いや、もうできないです。そもそも自分の中に選択肢として存在していないし、たとえ求められたとしてもできないです」とY.Uさんは断言する。
高校時代には不登校を経験し、留学も経験したY.Uさん。「不登校って、今でも大きな社会課題、というか、究極的な教育課題のひとつとして存在していると思うんです。でもその中で、自分は“良いこと”とは言い切れないかもしれませんが、別の選択肢があって、それを選べた側の人間だったと思っています。」そのような自覚が、恵まれない環境にある人々への問題意識を高めることになった。
大学では社会学を専攻し、社会理論の枠組みから「社会への貢献とは何か」を見つめ直し、そこから「どのような変化が必要なのか」「何が起これば社会は変わるのか」といった視点で考えていました。理論と実践の両面から社会課題にアプローチする視点を養っていった。
学部時代からNPOでのインターン経験も積んだY.Uさんだが、そこで「感情労働のような仕事が多くて、正規職員の方でもメンタルが限界を迎えて休職されるケースも目にしました」。そんな現実も、彼は目の当たりにしてきた。そして、「非営利で、資本市場や経済合理性の外に置かれると、それはそれでうまくいかない部分がある」という気づきが、やがて“持続可能なモデル”への関心へとつながっていく。
さらに、公務員になる選択肢について話が及ぶと、Y.Uさんは「官僚は、たぶん絶対に無理ですね。僕、週刊誌に情報を流しちゃうタイプだと思うんで!」と笑いながら語る。
「自我が強いので、“これおかしいだろ”って思ったことは、たぶん全部口に出しちゃうし、流しちゃうと思うんです」と続け、自身が組織の中で“空気を読んで沈黙する”ような働き方には向いていないと語った。こうした経験から、Y.Uさんは「非営利×持続可能なモデル」という独自の価値観を形成していった。それは、社会課題の解決と経済的持続可能性を両立させる道を模索するものだった。
ファーストキャリアとして日本財団を選んだ理由
Y.Uさんが最終的に日本財団を選んだ背景には、彼の価値観と日本財団の事業モデルが深く合致したことがある。
——日本財団を選んだ決め手は何だったのでしょうか?
「説明としてはあまり整理されていないかもしれませんが……」と前置きしながらも、Y.Uさんは日本財団の魅力について語り始めた。
「まさに日本財団は、その“間”を担っているということが、自分にとってすごく印象的で、良いと思っている点なんです。何かしらのモデルをつくる、つまり、課題解決の初期フェーズにおけるモデルづくりを実際に担っているところが、すごく面白いと思っています」とY.Uさんは説明する。。
日本財団の活動プロセスについて、Y.Uさんはこう説明する。
「モデルづくりのために助成金を出して、それが“うまくいった”となれば、行政への政策提言を行ったり、行政と一緒に制度化に向けて動いたりするんですね。つまり、現場から制度までの間をつなぐ“媒介者”としての役割を担っているのが、まさに日本財団だと感じています。」
この“媒介者”としての立ち位置は、Y.Uさん自身が抱いていた思いとも重なる。
「社会課題にアクセスできるし、それでいて官ではない。民間の立場なので、ある程度の対価も得られる」——そんな希望に、日本財団のポジションは合致していた。
——ご自身の強みと日本財団の仕事の関係はどう捉えていますか?
「これまで自分がやってきたことって、まさに“現場”と“抽象”を行き来するようなことだったと思うんです」とY.Uさんは語る。「インターンでは、メディアやNPOといった社会課題の現場に関わってきましたし、大学・大学院では理論的で抽象度の高い議論をずっとしてきました。だからこそ、その両方に触れられて、つなげていけることこそが、自分の価値になると思っていて」そして最終的に、「そういった価値を発揮できる会社、というか、そういう場に身を置きたいと思って、進路を決めました」と話す。
また、キャリアパスとしての魅力について、「ファーストキャリア財団ってなんかその後どうなるかわかんないじゃないですか」と述べ、「なんでそれで面白いかな」と感じたという。将来の可能性が開かれていることも、Y.Uさんにとっては魅力だったようだ。
これからの就活生へ:メッセージと再現性
Y.Uさんの就活経験は、これからの就活生にとって貴重な示唆を含んでいる。
——就活生へのアドバイスはありますか?
「アドバイスというほどのものはないんですけど、BaseMeを使っておいて損はないと本当に思っていますね」
そう前置きしながら、Y.UさんはBaseMeの良さについて語る。
「いろいろな就活サイトやスカウトサービスがあると思うんですけど、BaseMeは送られてくるメッセージに“プロフィールをちゃんと見てくれている感”があるんですよね」と、その丁寧さを評価する。
BaseMeを通じて「カジュアル面談のお誘いが来たら申し込む」というスタンスで就活に臨んだY.Uさん。
「採用情報とか、けっこう連絡もらってたんですけど、まあ正直、内容は玉石混交ではありました」としつつも、「自分が関心を持っていた領域だったので、結果的にはすごく良かった」と振り返る。
また、「この人、本当に会いたいと思ってくれてるんだろうな」と感じられる点も、高く評価している。
「一斉送信じゃない」「ちゃんとターゲットを見て送ってる」「みんながその“期待”で登録している」——そんな信頼感が、BaseMeにはあるという。
——最後に、これからの就活生に伝えたいことはありますか?
「ファーストキャリア、大事ですよね。後悔のない道をぜひ進んで欲しいと思います。