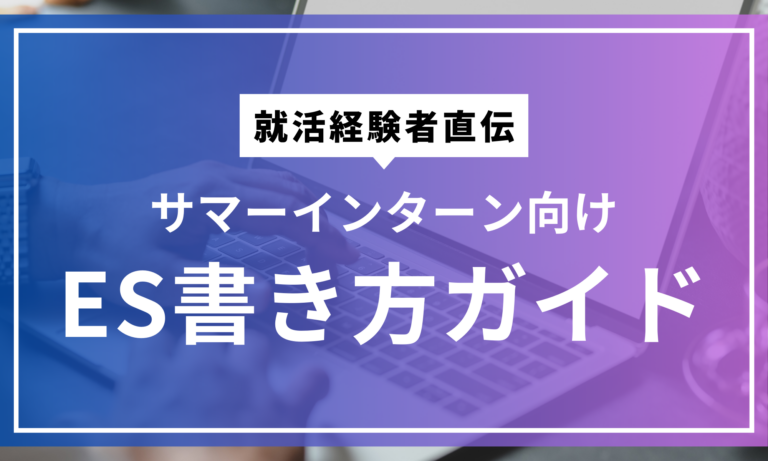はじめに
サマーインターンのES(エントリーシート)は、就職活動の第一歩となる重要なステップです。周囲の学生に圧倒されて不安を感じることもあると思いますが、就活初期だからこそ、自分が大切にしていることを素直に見つめ直し、それを言葉にしていくことが重要になってきます。評価されるのは、どんな経験をしたかではなく、その経験から何を考え、どう行動したかというプロセスです。そこにこそ、あなたらしさが自然と表れます。
ESでは、他の人と違う経験を書くものではなく、自分の経験に自分なりの視点で意味を与えることが大切です。また、ESを書く目的は、選考に通るためだけではありません。自分の価値観や強みを言語化し、「自分に合う環境とは何か?」を考えるきっかけにしてください。
本記事では、サマーインターンのESで自分らしさを伝えるための考え方や書き方のコツを、実際の例文を交えながら紹介します。内定獲得を目指すだけでなく、自分に合った環境を見つける第一歩として、ぜひ活用してください。
サマーインターンのESとは?
サマーインターンの選考において、最初に立ちはだかるのがESです。限られた文字数の中で、自分の強みや想いを伝える必要があり、多くの就活生にとって最初の壁となる存在でもあります。
この章では、「そもそもESとは何か?」という基本から、本選考との違い、企業がESを通じて見ているポイントまで、わかりやすく解説します。サマーインターンの第一関門を突破するために、まずはESの役割と重要性を正しく理解することから始めましょう。
ESの基本的な役割
ESとは、インターンシップや本選考の初期段階で多くの企業が課す提出書類です。志望動機、自己PR、学生時代に力を入れたこと(いわゆる「ガクチカ」)など、学生の人となりや思考の傾向を知るための質問が設けられています。
企業ごとにフォーマットや文字数、設問内容は異なりますが、いずれも「この人ともっと話してみたい」と思われるかが評価の分かれ目となります。
本選考とインターンシップの相違点
本選考では入社後の即戦力となるかどうかが重視される一方、サマーインターンでは将来性、思考の柔軟さ、学ぶ姿勢など、ポテンシャルが評価される傾向があります。
多くの企業が、サマーインターンのESで特に注目しているのは、論理的思考力や課題解決力、コミュニケーション力などの基礎的な能力です。たとえば、自己PRからは自己理解の深さや独自の考えを持っているかが評価されています。
また、企業への関心度や理解度も重要な評価ポイントです。企業の事業内容や取り組みにどれだけ共感し、自分とのつながりを見出しているかを伝えることで、「この人は真剣に参加を考えている」と評価されるきっかけになります。
ESが選考の第一関門である理由
サマーインターンには多くの学生が応募しますが、参加枠には限りがある狭き門です。そのため、ES段階で多くの応募者が選考から外れることも少なくありません。
だからこそ、ESでは単に上手く書くことよりも、自分の考えを丁寧に伝えることが重要です。自分らしさが伝わるESを書くことができれば、面接や実際のインターンでのやりとりにも好影響を与えるでしょう。
サマーインターンESで企業が見ている3つのポイント
サマーインターンのESでは、「その人がどんな考えを持ち、どんな価値観を大切にしているか」が重視されます。企業はESを通して、「この学生と話してみたい」と思える材料を探しています。ここからは、企業が注目している主な3つの視点を紹介します。
① 目的意識
企業は「自社に対してどれだけ興味を持ってくれているのか」「なぜ数ある企業の中から自社を選んだのか」という応募理由の明確さを重視しています。「とりあえず応募しました」「インターンに行けば何か分かると思った」などの曖昧な理由では、相手の心を動かすことはできません。
まずは、「その業界や職種にどんな関心があるのか」をはっきりさせましょう。たとえば、「IT業界の変化の速さと、それに柔軟に対応する企業文化に惹かれた」「モノづくりの現場を自分の目で見て、リアルなビジネスの流れを学びたい」といったように、具体的な関心のきっかけや知りたいことを言語化することで、ESに説得力が生まれます。
② 共感性
どんなに優秀な学生でも、企業との相性がなければ長く働くことは難しいです。企業側もそれをよく理解しています。だからこそ、ESでは価値観の共鳴が重要視されます。
たとえば、「『変化を楽しむ』という社風に共感した」「若手でも裁量を持ってチャレンジできる環境に惹かれた」「社員インタビューで語られていた『現場主義』の考え方に強く共感した」といったように、企業の考え方や文化に共鳴した点を伝えることで、「この人は自社との親和性が高いかもしれない」と好印象につながります。
単に興味があることを伝えるのではなく、なぜ共感したのか、その理由まで丁寧に書くことが大切です。
③ オリジナリティ・経験
企業が知りたいのは、実績の大きさではなく、具体的な行動やその過程で頭をめぐらせて考えてきたことです。部活のキャプテン、留学経験、学園祭の代表など、華やかな経験である必要はありません。
むしろ、アルバイトでの小さな工夫、チームでの意見の衝突をどう乗り越えたか、自分なりに継続してきた習慣といった日常の中での気づきや成長のエピソードの方が、あなたらしさが伝わりやすい場合もあります。
自分の言葉で、自分の目線から語るストーリーこそが、ESに深みを与えてくれるのです。
Step1|書き始める前にやるべきこと
サマーインターンのESは、就職活動本番とは異なり、数百〜数千人の応募者の中から、数十人を短期間のプログラムに招くための選考です。つまり、ES1枚から「この学生に会ってみたい!」と思わせることができるかがカギになります。
そのためには、形式やテンプレートにとらわれず、あなた自身が伝わる内容に仕上げることが重要です。いきなり書き始めるのではなく、まずはサマーインターンに臨む目的や、自分らしさの軸を明確にすることから始めましょう。
自己分析
サマーインターンのESで自分らしさを伝えるには、まず自分自身を理解することが不可欠です。「自分はどんな人なのか」という問いに向き合うために、どんなことをしている自分が好きなのか、どんなときに違和感を感じたかなど、これまでの人生を振り返ってみましょう。
そうすることで、自分の価値観や行動のクセが見えてきます。エピソードの大きさにこだわらず、自分が何に反応してきたかを丁寧に言語化していくことがポイントです。
自己分析に関しての詳しい情報は、【就活初心者必見】自己分析でもう困らない!目的・やり方・活用術まで徹底解説 でもご覧いただけます。自己分析の目的や具体的な方法、自己分析結果の活用術まで、具体例とともに解説しますので、ぜひ参考にしてください。
企業分析
企業分析と聞くと、ホームページに載っている事業内容や売上、業界順位などの数字に目が行きがちですが、それだけでは本質的な理解にはなりません。本当に知るべきなのは、その会社が何を大切にしていて、どんな人たちが、どんな思いで働いているのかという部分です。特に、サマーインターンの選考が始まる就活初期の段階で、企業分析の正しい視点を身につけておくと、良いスタートを切ることができます。
選考対策のためだけでなく、自分に合う会社かどうかを見極めるためにも、表に出ている情報に加えて、実際に働く人の声の両面から立体的に企業を見ることが大切です。
以下に、企業研究を進める上で押さえたい10の視点をまとめました。自分で人に説明できるレベルを目指して整理してみましょう!
【公開情報ベース:自分で調べて分かること】
| ① 企業理念 | 会社がなぜ存在し、何を目指しているのか、また、その言葉がどれだけ社員に浸透しているかも含めてチェックしましょう。理念が現場でどう息づいているかを社員インタビューなどで確認できるとベストです。 |
| ② 事業内容 | 商品やサービスの説明だけでなく、「どんな顧客に、どんな価値を提供しているのか」に着目すると、仕事のよりリアルな側面に触れることができます。 |
| ③ 成長性・利益水準 | 売上や利益の伸び率を3〜5年スパンで確認することで、会社の成長フェーズや将来性が見えてきます。安定企業か、成長ベンチャーかなどの判断材料としても活用できます。 |
| ④ 成長戦略 | IR資料やトップメッセージなどから、会社が今後どこを目指しているかを読み取ってみましょう。変化の方向性と自分の興味が重なると、選考でも自然と熱量が高まっていきます。 |
| ⑤ 給与水準・評価制度 | 単に「給料が高いか安いか」だけでなく、どんな基準で評価されるのか、成果主義なのか年功序列なのか、自分に合った制度かを見極める視点が大切です。 |
【現場の声ベース:実際に話を聞いて初めて分かること】
| ⑥ 企業文化 | 「上下関係はフラット?縦社会?」「挑戦が歓迎される?慎重さが求められる?」など、企業の中に流れる目に見えない文化を探りましょう。座談会やOB訪問での質問が有効です。 |
| ⑦ 活躍する社員像・求める新卒像 | 選考では会社が求める人物像とのフィット感が重視されます。実際に活躍している社員の特徴や、新卒に求める力を知ることで、自分がマッチするかが見えてきます。 |
| ⑧ 入社後すぐの仕事内容 | 配属後すぐの業務内容によって、成長のスピードも身につくスキルも変わります。「入ってから何ができるのか?」を具体的にイメージできると志望動機にも深みが出ます。 |
| ⑨ 業務外で関われる制度 | 研修制度や社内制度、異動・副業・社内起業制度など、制度から見える会社の「人材への投資姿勢」もチェックポイントです。 |
| ⑩ キャリアの描き方 | その会社で働くと、自分はどんな経験を積み、どんなキャリアが描けるのでしょうか? 実際の先輩のキャリア事例を聞くと、自分の未来をより具体的に想像できるようになります。 |
自分に問いかける3つの質問
次に、サマーインターンのESを書く前に考えておくべき3つの問いを紹介します。選考に通るためのESを目指すのではなく、自分が納得のいくインターン選び・企業選びをするための土台づくりにもつながります。自分自身にしっかりと向き合いながら、その企業に行きたい理由や知りたいことがESににじみ出るような内容にしていきましょう。
- どんな環境ならワクワクするか?
これまで自分がワクワクしたポイントを遡り、自分が楽しく働けるのかどんな場所か、想像してみてください。自由度が高く挑戦が歓迎される環境なのか、静かにじっくり物事を考える時間がある職場か、あるいはチームで協力しながら進めていく仕事なのかなどなど、「こういう環境なら自分らしくいれる」と思えるイメージを持つことで、企業選びや志望動機がより具体的になります。
- どんな時に力を発揮できたか?
過去の経験の中で、「自然と頑張れた」「自分はそこまで苦労していないが周囲の人からたくさん褒められた」と感じた瞬間を思い出してみてください。プレッシャーの中で集中できた場面、周囲のサポート役に回って信頼された体験、小さなことでも継続したことが評価された時など、これらは、他の人にはない、あなただけの強みや個性のヒントです。
- このインターンで知りたいことは何か?
「ただ参加してみたい」だけではなく、「この機会を通じて何を得たいか」を明確にすることも大切です。社内の意思決定のスピード感を体感したい、現場社員が何にやりがいを感じているのかを知りたい、実際のプロジェクトの進め方を学びたいといったように、目的がはっきりしていると、企業側にも「この学生は意欲的だ」と伝わります。
Step2|項目別ESの書き方と例文紹介
ここからはいよいよ、サマーインターンのESを書き始めるステップに入ります。各項目の書き方のポイントを押さえながら、例文も交えて丁寧に解説していきます。
大切なのは自分の言葉で語ることです。企業が知りたいのは、完成された文章ではなく、あなた自身の価値観や人柄であることを忘れないでください。
これから紹介する構成や例文をヒントにしながら、自分の経験とじっくり向き合い、「なぜこの企業なのか」「自分はどんな人間なのか」を自分自身の言葉で言語化していきましょう!
志望動機
志望動機は、「なぜその企業でなければならないのか」を伝える大切な項目です。インターンに参加したいと思ったきっかけや、企業の理念・ビジネスにどんな共感を覚えたかを軸に書くことで、あなたと企業との接点が浮かび上がります。
ここで大切なのは、「成長したいから」「業界に興味があるから」だけでは差別化が難しいということです。企業ごとの言葉や価値観に、自分の過去の経験や考えがどう重なるかを言語化することで、説得力のある志望動機になります。
例文:
私は「挑戦する人を応援する社会をつくる」という貴社のビジョンに強く共感し、インターンに応募しました。私自身、大学の学生団体で挑戦を恐れていた仲間の背中を押した経験があり、「誰かの一歩を支える」仕事に惹かれています。現場での仕事を通じて、貴社の価値観がどのように体現されているのかを学びたいと考えています。
自己PR
自己PRでは、自分の強みをただ述べるだけでなく、過去の経験を根拠に、その強みがどんな場面で役立つのかを具体的に描くことがポイントです。企業の仕事において、あなたの強みがどんな貢献につながるかを想像しながら書いてみましょう。
また、「バイトリーダーをやっていた」などの表面的な肩書きよりも、自分の行動や思考、周囲への影響などに焦点を当てると、よりあなたらしさが伝わります。
例文:
私の強みは「ひとりひとりの想いを汲み取る力」です。大学のオープンキャンパス運営で、メンバーの意見がぶつかった際、それぞれの背景を丁寧に聞き取り、納得感のある形で合意形成を図りました。この強みを、チームで価値を生み出す場面で活かしたいと考えています。
自己PR・志望動機に関してより詳しく知りたい方は、【例文多数】自己PRと志望動機の書き分け、コツ、例文をまるごと解説 を参照してください。
学生時代に力を入れたこと
学生時代に力を入れたことは、あなたがどんな場面で、どんな行動をし、何を学んだかを伝えるチャンスです。注目すべきは、インパクトの強い成果ではなく、課題にどう向き合ったか、どんな価値観がにじみ出ているかです。
自分が自然に頑張れた経験や、大変だったけど振り返ると得られたものがある経験に目を向けてみましょう。その中に、あなたらしい思考やエネルギーの源があります。
ポイントはエピソードをひとつに絞ることです。エピソードが複数ある場合も全てを盛り込もうとせず、何か課題に対してアクションを起こし、それを通じて自身が成長した経験を選ぶと良いです。
以下のような流れに沿ってエピソードを整理すると、内容が伝わりやすくなります。今回は「STARフレーム」をご紹介します。
STARフレーム(Situation/Task/Action/Result)は、自分の経験を論理的かつ魅力的に伝えるための構造です。どのように自分が課題を捉え、どのように工夫し、何を得たのかを、読み手が自然に理解できるように整理するためのフレームです。「なぜその行動をとったのか」「何を考えていたのか」「その経験を通して自分にどんな変化があったのか」といった思考のプロセスを、因果関係とともに描くことが大切です。
- 状況(Situation):いつ、どこで、どんな背景で起きた話なのかをなるべく簡潔に書き、読み手が状況をすぐにイメージできるようにします。
- 課題(Task):求められていた役割・達成目標ではなく、自分が何に問題意識を持ち、何を乗り越えようとしたかを書きます。ここに自分らしい視点が出ます。
- 行動(Action):「なぜその行動を選んだのか」「どう工夫したのか」など、思考や工夫が見えるようにします。自分の価値観や判断基準が伝わる部分です。
- 結果・学び(Result):取り組みの結果、どんな変化・成果があったか、そしてそこから何を得たのかを書いていきます。その学びを今後どう活かしたいかまで書けるとなお良いです。
例文:
S(状況)
大学1年のとき、地元商店街の空き家を活用し、地域活性イベントの企画・実施に取り組みました。きっかけは、まちづくりを学ぶゼミで「地域の人の声を聞く」というテーマに惹かれたことでした。
T(課題)
しかし、企画初期には、自治体や商店主の方々との連携が思うようにいかず、「外から来た大学生が何をしに来たのか」と疑念を抱かれることもありました。私は、その違和感の正体は「関係性ができていないこと」にあると考え…
A(行動)
…地元の方との対話に時間をかけるよう意識しました。商店街に何度も足を運び、話を聞き、食事をご一緒させてもらいながら、少しずつ信頼関係を築いていきました。
R(結果・学び)
その結果、イベント当日は地域住民や学生含め200名以上が参加し、「こんなに人が集まったのは久しぶり」と喜んでもらうことができました。この経験から、人との関係づくりや相手の立場に立った対話の大切さを実感し、「誰かの声に寄り添い、形にすること」にやりがいを感じるようになりました。今後も、関係性を土台に価値を生むような取り組みをしていきたいです。
サマーインターンで学びたいこと
「このインターンで何を学びたいのか?」という問いには、自分の課題意識や、成長したい方向性を交えて答えましょう。ここでも重要なのは、ただ学びたいだけでなく、「なぜその学びが今の自分に必要なのか」を具体的に示すことです。
企業から見れば、「この学生は、何を考えて、どんな成長を求めているのか?」を知ることで、現場での吸収力や適応力をイメージできます。
例文:
貴社の「意思決定スピードの速さ」に興味を持っています。自分が情報を集め、仮説を立て、行動に移すまでに時間がかかる傾向があると感じており、スピード感ある現場で「考えながら動く力」を養いたいと考えています。
Step3|書いたESを見直すチェックポイント
ESを書き終えたら、そのまま提出するのではなく、一度立ち止まって「読み手目線」で見直してみましょう。丁寧に書いたつもりでも、伝えたいことが正しく届いているとは限りません。
ここでは、仕上げの精度を高めるために大切な3つのチェックポイントをご紹介します。最終チェックリストも参考にしながら、書いたESを改めて確認してみましょう!
結論は最初に書けているか
読み手は「この人は何を伝えたいのか?」を真っ先に知りたいと思っています。だからこそ、伝えたい主張や結論は最初に書きましょう。冒頭に明確な結論があると、ES全体の構造も理解しやすくなり、読み手に安心感を与えます。「最初の1文で言いたいことが伝わるか?」を意識して読み返してみるのがおすすめです。
自分ならではの言葉・感情が含まれているか
ESは誰でも書ける内容ではなく、「あなたしか書けないストーリー」であることが大切です。テンプレート的な表現ではなく、自分の経験から出てきたリアルな言葉や感情が含まれているかを見直してみましょう。「この一文、自分で書いたときに胸が動いたか?」という観点で振り返ると、本音が表現できているかを確かめやすくなります。
誰にでも伝わるわかりやすい表現になっているか
就活に限らず、伝える力の本質は、相手にきちんと届くかどうかです。専門用語や抽象的な比喩は、読み手によって誤解を生むことがあります。身近な人に読んでもらい、引っかかるところがないかどうかを確認するのも非常に有効です。特に初めて読む人でもすっと理解できる表現になっているか、文章の「わかりやすさ」を最後に意識して仕上げましょう。
【最終チェックリスト】
| □ 結論は最初に書かれているか? |
| ・冒頭で「何を伝えたいのか」が一文でわかるようになっているか |
| ・読み手が最初の数行で、主張の軸をつかめる構成になっているか |
| □ 自分ならではの言葉・感情が含まれているか? |
| ・誰にでも当てはまるテンプレ的な表現になっていないか |
| ・自分の経験や思いから自然に出てきた生の言葉になっているか |
| ・書きながら「これは自分らしい!」と思えるポイントがあるか |
| □ 誰にでも伝わるわかりやすい表現になっているか? |
| ・抽象的な言葉や専門用語に頼りすぎていないか |
| ・例え話や比喩が複雑すぎていないか |
| ・家族や友人に見せて、内容がすっと伝わるかを確認したか |
| □ 誤字・脱字・文章のねじれはないか? |
| ・誤字脱字や、主語と述語の不一致がないか |
| ・句読点の位置や改行のタイミングに違和感はないか |
| ・読み返して、声に出して読んでも自然な流れか |
まとめ
サマーインターンのESは、単なる選考対策ではありません。「どんなことにワクワクするのか」「どんな価値観を大切にしたいのか」といった、自分の原点と向き合う非常に貴重なプロセスです。ESを書く中で見えてきた自分らしさは、その後の就活やキャリア選択の軸になります。たとえインターンに参加しなくても、その過程で得た気づきは必ずあなたの糧になるはずです。
そして、心を込めて書かれたESは、飾った言葉よりもずっと、読み手の心に届きます。等身大のあなたがにじむような書き方こそが、あなたに合う企業との出会いを引き寄せてくれるのです。悩んで立ち止まりながらも、自分の言葉や書き方で一歩ずつ書き進めたESには、あなただけの価値観と魅力が宿ります。この記事では、そんなESの書き方のヒントをお届けしてきました。焦らず、背伸びせず、自分らしい表現で、まずはその一歩を踏み出してみてください!