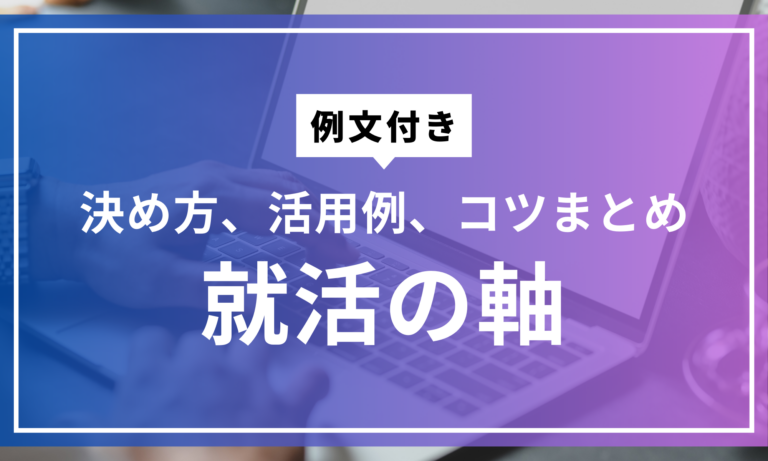就活をしていると「あなたの就活の軸はなんですか?」という質問を受けることがあります。就活の軸を考えることは、就活のみならず、キャリア設計の上でとても重要なプロセスです。
本記事では、「就活の軸」の決め方や活用法、そして就活の軸を定めるためのコツまで徹底的に解説します。記事を読んで、精度の高い「就活の軸」とともに、自分らしいキャリアを歩んでいきましょう!
就活の軸とは
「就活の軸」とは、仕事を選ぶときに自分が大事にする考え方や基準のことです。無数にある企業から自分にあった企業を選ぶためには、選択肢を絞り込むための基準が必要です。その判断基準を定めたものが「就活の軸」です。自分が持っている価値観や、展望、企業に求める条件などが「就活の軸」となり、最終的に就職先の企業を決定するまで繰り返し使われます。
就活の軸が大切なのはなぜか
納得度の高い就活をするためには、就活の軸は欠かせません。就活をする上で就活の軸を持つことが重要な理由を3つにまとめました。
企業選びの基準が明確になる
就活の軸を決めることによって、企業選びの基準を明確にすることができます。つまり、自分に合った企業を見つけやすくなります。
就活を進めていくと多くの企業に出会います。しかし、企業によって仕事内容や社風などが異なります。その中から自分に合った企業を選択するためには、譲れないポイントやこだわりなどを自分自身で把握すること=「就活の軸」をはっきりさせることが重要なのです。
企業比較がしやすくなる
就活の軸を定める理由のひとつに、企業比較がしやすくなることが挙げられます。就活の軸を決めておくと、企業同士を比べる観点が明確になります。
就活では、多くの企業を研究したり、説明会に参加することになるでしょう。最終的には就職先の企業をひとつ選ばなければいけませんが、その過程で何も基準がないと、企業の比較ができずに迷ってしまいます。
企業を比較する要素は無数にあります。たとえば、「成長環境があるか」「ワークライフバランスを大切にできるか」を就活の軸に設定するとします。すると、複数の企業の比較をする際に、企業ごとの特性を理解しやすくなり、自分にとって最適な企業の選択が容易になります。一方で、就活の軸が曖昧のまま企業を比較しようとすると、「給料が高いから良さそう」「なんとなく福利厚生が良さそう」といった本来重視していなかった要素を基準に判断してしまう可能性があります。
就活の軸を定めることで、企業を比較するポイントが明確になり、自分に合う企業を冷静に判断できるようになるのです。
自己分析が深まり成長につながる
就活の軸を持つことによって、自分の価値観や大切にしたいことをしっかり理解できるようになり、人として成長できる機会につなげることができます。
就活では、「どんな仕事がしたいのか」「どんな環境で働きたいのか」といった要素を考える必要があります。しかし、これらを考える前にまず、自分がどんな人間なのかを理解することが重要です。
就活の軸を定めるプロセスの中で自己分析をおこなうと、自分が大切にしている価値観や向いている仕事の特性が明らかになっていき、やがて就活の軸を形作ります。たとえば、自己分析をして「新しいことに挑戦するのが好き」という自分の傾向を見つけたとします。ここから「若いうちから成長できる環境がある」という就活の軸を決めることができ、自分のとって大切な要素を重視して就活を進めることが可能になります。
就活の軸を定めることは、自分がどんな人間なのかをより深く知り、成長するための重要なステップです。
企業が就活の軸を求める理由
企業の選考プロセスの中で「あなたの就活の軸はなんですか?」といった質問を受けることがしばしばあります。企業は学生に就活の軸を聞くことで、何を知りたいのでしょうか。ここでは、企業が就活の軸を求める理由をまとめました。企業が就活の軸を知りたい理由を理解することによって、就活の軸は学生のみならず、企業側にとっても重要なものであると確認できるでしょう。
自社との価値観の一致を確認するため
企業が就活の軸を求める理由のひとつに、「自社と価値観が一致しているかを確認するため」ということが挙げられます。企業は就活の軸を「自社の価値観と合っている人材か」を判断するための材料として活用しています。
企業ごとに、仕事上で大切にしている考え方や仕事の進め方が異なります。また、異なる価値観を持つ人材を採用した場合、入社後のミスマッチを招く可能性が高まります。そのため、企業は自社の価値観に合う人を採用したいと考えて採用活動をおこなっています。
企業が就活の軸を求めるのは、お互いにとって良いマッチングかどうかを慎重に確認しているからなのです。
志望度や入社後の定着度を測るため
企業は就活生が本当に自社に合っているか、長く働いてくれるかを判断する材料を集めるために、就活生に就活の軸を尋ねています。
自分の軸に合った企業に入社した人は、働く目的が明確なので、仕事への満足度が高く、長く働きやすくなります。たとえば、「人と関わる仕事がしたい」という軸で営業職を志望している人は、仕事にやりがいを感じやすく、満足感を持って仕事に向き合える可能性が高いと考えられます。
企業の特徴と就活生の軸がマッチしていない状態で採用してしまうと、お互いにとって不幸を招くかもしれません。企業はそれを防ぐために就活の軸を聞いて、企業と就活生の相性を見極めているのです。
論理的思考力を確認するため
企業は就活生に就活の軸を尋ねる過程で、物事を筋道立てて考え、分かりやすく説明できる力があるかをチェックしています。
仕事の場面では、論理的思考力が大変重要視されます。上司や同僚、お客様に対して、自分の考えを論理的に説明する力が求められます。入社前から物事を論理的に伝えられる人は、入社後も活躍しやすいと判断されるため、就活の軸を尋ねることによって、論理的思考力が備わっているかを確かめています。
企業は就活の軸を質問することで、主に次のようなポイントを見ています。
考えが一貫しているか
就活の軸で挙げられた要素と、企業に求める環境が一致しているため、一貫した考えを持っていることが企業担当者に伝わります。
理由が明確であるか
就活の軸を決めた背景が論理的に説明されているので、説得力の高い説明になっています。
このように、企業は就活の軸を尋ねることで、論理的に考えられるかどうかを確認しています。そのため、就活の軸を決めるときには、相手が納得できるように説明できるよう、思考を整理しておくことが重要です。
就活の軸の決め方・見つけ方の切り口5選
就活の軸を定めることが重要だということがわかりました。では、就活の軸はどのように決めたら良いのでしょうか。この章では、就活の軸を決めるための考え方の切り口を5つ紹介します。なるべく多くの切り口を試してみることによって自己理解がより深まるので、複数個の切り口で考えてみることをおすすめします。
自己分析をする
自己分析は、就活の軸を決める上で土台となるプロセスです。自分の価値観や強み・弱みを把握することで、自分に合った企業を選びやすくなります。
自己分析をおこない、「自分はどんな人間なのか」を深く理解すると、仕事に求める要素を見つけることができます。反対に、自己分析をおこなわないと、就活の軸を決めることは困難でしょう。自己分析をして自己理解を深めることは、自分に合った企業を選ぶ上で重要なステップなのです。
将来の理想像を考える
就活の軸を定めるための思考の切り口として「将来の理想像を考える」ことも有効です。自分がどんな社会人になりたいのかをイメージすることで、それに合った企業を選ぶことができます。
就活はゴールではなく、キャリアを歩むためのスタート地点です。目の前の「内定をもらうこと」に焦点を当ててしまうと、入社後のミスマッチを引き起こす可能性が高まります。そのため、キャリアに求めることを明らかにすること、つまり将来像を言語化することが重要です。将来の理想像を考えることで、自分に合った企業の条件が明確となり、就活の軸が自ずと定まっていきます。
企業研究を通じて興味関心を深める
就活の軸を決めるために企業研究に注力することもひとつの有効的な方法です。さまざまな企業を調べることで、自分が本当に興味を持てる業界や仕事を見つけ、就活の軸を明確することができます。
特に就活を始めたばかりの段階では、「どんな仕事が向いているのか分からない」「自分が何をしたいのかハッキリしない」と悩む人が多いです。そんなときに役立つのが企業研究です。企業研究をすることで、働き方のイメージが広がる、自分の興味分野を発見できるといったメリットがあり、就活の軸を考えやすくなります。
この時、最初から業界や職種を絞り込まず、幅広く調べるようにしましょう。業界や職種に対する固定概念や過った認識を改めることで、自分の可能性を広げることにもつながります。
社会人や先輩に話を聞く
就活の軸を決めるためのプロセスとして、社会人や先輩に話を聞くことも有効な手段のひとつです。実際に働いている人の話しを聞くことで、仕事のリアルなイメージを持つことができ、自分に合う企業や働き方を見つけやすくなります。
就活をしていると、企業のホームページや求人情報を読む機会が増えますが、実際の働き方や職場の雰囲気は、なかなかイメージしづらいものです。実際にその企業で働いている社会人や、就活を経験した先輩から話を聞くことでリアルな情報を得ることができ、現実に沿った就活の軸を考えることができるようになります。
たとえば、社会人や先輩の話を聞く中で、「この業界はやりがいがありそうだけど、思っていたより忙しそうだ」という印象を受けた場合、自分にはワークライフバランスを重視する傾向があることがわかり、就活の軸が定まります。同様に、「成長環境が整っていると聞いてワクワクした」のであれば、若いうちから成長できる環境を重視するという新しい就活の軸を決めることができます。
このように、社会人や先輩に話を聞くことで、自分が何を大切にしたいのかが明確となり、就活の軸を定めるヒントを得ることができます。
他の就活生と意見交換をする
就活生の仲間と意見交換をすることも、就活の軸を定めるにあたって有効的な方法です。自分とは異なる考えや価値観に触れることで、就活に対する新しい視点を得たり、既存の自分の考えを深めたりすることができます。
就活は自己分析をはじめ、自分自身と向き合う時間が多くなります。一人で考えていると、視野が狭くなったり、検討できる選択肢が限られてしまうことがあります。一方で、同じように就活に取り組む他の学生と話すことで、自分の価値観を見つめ直したり、就活の進め方のヒントを得られたりと、新しい気づきにつながります。
他の就活生と意見交換をする際には、ただ雑談するのではなく、意識するポイントを知った上で取り組むとより有意義な時間を過ごすことができます。まず、お互いの就活の軸に対する考えを深め合いましょう。「企業選びで大切にしていること」「その業界を選んだ理由」などを深堀りして自分の軸と照らし合わせることで新しい発見があるかもしれません。また、就活の進め方や悩みを共有してみましょう。「企業研究の方法」や「面接対策の工夫」は人によってさまざまなので、新たな学びを得られる可能性が高いです。
就活では一人で考え込まず、積極的に他の人と話すことで、より明確な就活の軸を定めることができます。ぜひ周りの就活生と意見を交換してみましょう!
就活の軸を決めるときに気を付けるべきこと
ここまで就活の軸を決めるための切り口を紹介してきました。次に、実際に就活の軸を定める際に気を付けるべきポイントを解説していきます。以下の点に気を付けながら、質の高い就活の軸を準備して、納得した就活を進めていきましょう。
抽象的すぎる軸にしない
就活の軸を決めるときには、抽象的すぎる軸にしないことが重要です。たとえば、「成長できる仕事がしたい」「人の役に立ちたい」という軸は一見良さそうに見えますが、どんな会社にも当てはまるため、具体性が足りません。企業担当者に「うちの会社でなくてもいいのでは」と思われてしまう可能性があります。
以下のように具体的にすると、考え方がはっきりと示された明確な就活の軸になります。
- 「成長できる仕事がしたい」→20代から責任のある仕事に挑戦できる会社
- 「人の役に立ちたい」→教育業界で、子どもたちの学びをサポートする仕事
就活の軸を具体的にすることで、企業とのマッチ度をより高めることができます。
就活の軸を固定化しすぎない
就活の軸を定めることは重要ですが、最初に決めた軸にこだわりすぎず、柔軟に考えることが大切です。たとえば、「絶対に大手企業に入る」「この業界しか受けない」と決めつけてしまうと、選択肢が狭まり、良い会社と出会うチャンスを逃してしまう可能性があります。また、就活を進める上で自分の価値観や興味に変化が起きることもあります。
就活の軸を決めた過程やその理由に着目すると、就活の軸を定めつつ、固定化しすぎないという適度なバランスを保つことができます。たとえば、「大手企業にこだわる」という軸があったとき、大手企業が良い理由が「安定した環境で働きたい」「福利厚生が充実している」のふたつだったとします。すると、大手企業のみならず、安定していて働きやすい中堅企業やベンチャー企業も視野に入る可能性が出てきます。
最初に決めた就活の軸を基準としながらも、必要に応じて見直したり、その軸に至ったプロセスに着目したりすることで、より自分に合った企業を見つけることができます。
表面的な条件だけで決めない
就活は内定をもらうことがゴールではなく、キャリアをはじめる上での重要なプロセスです。この大事な過程で、表面的な条件のみを元に就活の軸を定めてしまうと、入社後の満足度の低下を招く可能性があります。
たとえば、「年収が高い会社がいい」「有名な企業に入りたい」「年間休日が多いところがいい」などの条件だけで会社を選ぶと、入社後のミスマッチを引き起こすリスクが高まります。これらの条件は重要ですが、実際の働き方や社風、価値観のマッチ度まではわからないからです。
「年収が高い会社がいい」と考えたとき、なぜ高収入が良いのかを考えてみましょう。「将来の安定のため」「やりがいのある仕事に見合った報酬を得たい」などの理由が明確になれば、そのために必要な環境や働き方が明らかになり、より深い条件を築くことができます。
会社の働き方や文化、自分の価値観との相性など、表面的な条件に留まらずに、それに至った経緯まで考慮して就活の軸を定めることが重要です。
就活の軸に関するよくあるQ&A
就活生からよく受ける、就活の軸に関するQ&Aをまとめました。多くの就活生が持つ「就活の軸」についての疑問をひとつずつ解消していきましょう。
「就活の軸」と「自己PR」は何が違うの?
就活の軸と自己PRは自分を良く知るという意味で似たものですが、その特徴や目的は大きく異なります。どちらも就活の面接の場面でよく問われるものなので、違いを明確にしておくことが重要です。
就活の軸は「自分が仕事を選ぶときに大事にする基準」のことです。就活の軸を決めることによって、どんな企業で働きたいかの思考が進みます。
一方で自己PRは「自分がその企業で活躍できることを示すアピール」のことを指します。自己PRで自分の強みを表現することによって、企業に「採用したい」と思わせることが目的です。
両者の違いを正しく理解し、使い分けられるようにしましょう。
「就活の軸」と「志望動機」が似てしまうのだけど良い?
就活の軸と志望動機が似てしまうという相談を、就活生からよく受けることがあります。しかし両者は異なるものなので、その違いを理解しましょう。その上で似てしまうことは問題ありません。
就活の軸は会社を選ぶときの基準である一方で、志望動機はその企業を選んだ理由を説明するものです。そのため、就活の軸は就活時期が同じであれば、すべての企業に対して共有のものが使用されます。しかし、志望動機は企業ごとに異なるものです。企業ごとの特性を理解した上で考えましょう。
志望動機では、就活の軸に加え、企業の特徴を入れると説得力の増した主張になります。就活の軸をベースにして、企業ごとにカスタマイズするのが志望動機と考えると良いでしょう。
就活の軸はいくつ持っておくべき?
就活の軸は2〜3つ持っておくと良いでしょう。
もし就活の軸がひとつのみの場合、企業を選ぶときの判断基準が狭まりすぎてしまい、自分に本当に合った企業を逃してしまう可能性が高まります。反対に、就活の軸が多いことも企業選びを難しくしてしまいます。就活において譲れない条件が多すぎると、すべてを満たす企業を見つけることが困難になり、どの企業を選べばよいのかわからないという問題が発生します。
終活の軸になりうる要素はたくさん存在します。その中から、「これだけは譲れない」と思うポイントを2〜3つに絞って就活の軸とすると、スムーズに就活を進めることができます。
面接で就活の軸を聞かれたらどうやって応える?
前章で、面接で就活の軸を聞くのは、企業側の目的があるということを学びました。その目的をしっかりと理解した上で、以下の3つのステップで回答すると、自分の考えを企業に伝えやすくなります。
まず、就活の軸を端的に伝えましょう。「私の就活の軸は〇〇です」という文章で十分です。
次に、その就活の軸を定めた理由を説明しましょう。その就活の軸を選んだ過程にこそ、あなた自身の価値観や考え方が反映されています。企業側も特に深く関心を示す箇所です。
最後に、就活の軸と志望企業とのつながりに言及して、志望動機に発展できると良いでしょう。志望動機にまでつながることを示せれば、一貫性のある回答になります。
就活の軸:業界不問 例文10選
志望業界や志望職種が定まっていない方も含め、すべての就活生が参考にできる就活の軸の例を10つまとめました。就活の軸とその活用例の例を参考にしながら、自分自身の就活の軸をぜひ考えてみてください。
社会に貢献できる仕事をしたい
社会に役立つ仕事がしたいという軸を大切にしています。私は学生時代、地域のボランティア活動を通して社会貢献の重要性を感じました。自分の働きかけが社会に良い影響を与えられるということが実感できる仕事にやりがいを感じます。
自分の意見を尊重される環境で働きたい
私は自分の意見をしっかり伝え、尊重される環境で働くことを重視しています。風通しが良く、立場に依らず誰もが意見を交わしやすく、考えが反映される職場に魅力を感じます。
グローバルな視野で働きたい
国際的な環境で働きたいという軸を持っています。私は小学生時代をアメリカで過ごしたバックグラウンドから、多様な人材の集まると多彩なアイデアが生まれることを実感しています。多国籍なチームで、国際的な経験を積みながら仕事をしたいと考えています。
自己管理を大切にしたい
自己管理をしっかりとおこないながら仕事を進める環境を求めています。大学生活では、勉強、アルバイト、サークル活動、ボランティア活動など多くのことを並行しておこなっていたため、自己管理の重要性を強く実感しました。人生の時間を有意義に使うために、目標を達成に向けた自己管理能力を磨いていきたいです。
仕事を通じて人々の生活を豊かにしたい
人々の生活を豊かにできる仕事をしたいです。学生時代にアルバイトで介護職の仕事を経験し、人と接する仕事にやりがいを感じました。直接的に人々に影響を与える仕事に興味を持ったため、サービス提供者が見える環境で働きたいです。
顧客に寄り添ったサービスを提供したい
私の就活の軸は、顧客に寄り添ったサービスを提供することです。大学時代、アルバイトで接客業をしていた際に、お客様一人ひとりのニーズをしっかりと把握し、それに基づいて対応することが非常に重要だと実感しました。
自分のアイデアを実現できる仕事をしたい
自分のアイデアを形にできる環境で働きたいです。大学時代、サークル活動でイベント企画を担当した際、自分のアイデアを形にする喜びを強く感じました。貴社では、新しいアイデアを活かして商品開発やサービス向上に貢献できると考えています。
チームワークを重視したい
私はチームで協力して成果を出すことに魅力を感じています。大学時代、ゼミのグループプロジェクトで、メンバーと協力して目標を達成する楽しさを実感しました。個人の力だけではなく、周りと協力して目標を達成することが大切だと思っています。
成長できる環境で働きたい
私の就活の軸は、自己成長できる環境で働くことです。大学時代の長期インターンシップでは挑戦を後押ししてくれる環境に恵まれ、やりたいことへのチャレンジを重ねることが出来ました。この経験から、成長できる環境で自分のスキルをさらに伸ばしたいと考えています。
新しい技術を活用する仕事をしたい
新しい技術を活用した仕事をしたいという軸があります。大学では最新のテクノロジーの活用を模索し、勉学と課外活動の両面からアプローチを続けてきました。テクノロジーを活かして、未来の社会を作る仕事に携わりたいと思っています。
まとめ
就活の軸を決めることは、自分にとって何が大切なのかを明確にし、企業選びを効率的におこなうための第一歩です。就活の軸を持つことで企業とのミスマッチを減らし、より納得のいくキャリア選択が可能になります。
しかし、就活の軸はあくまで就活をスムーズに進めるためのツールです。就活の軸を定める過程でキャリアに関するヒントを得たり、新しい自分の一面を見つけられたりするかもしれません。就活の軸を上手に活用しながら、自分らしいキャリアを描いていきましょう!
\就活の軸を自分らしく定めたいなら/