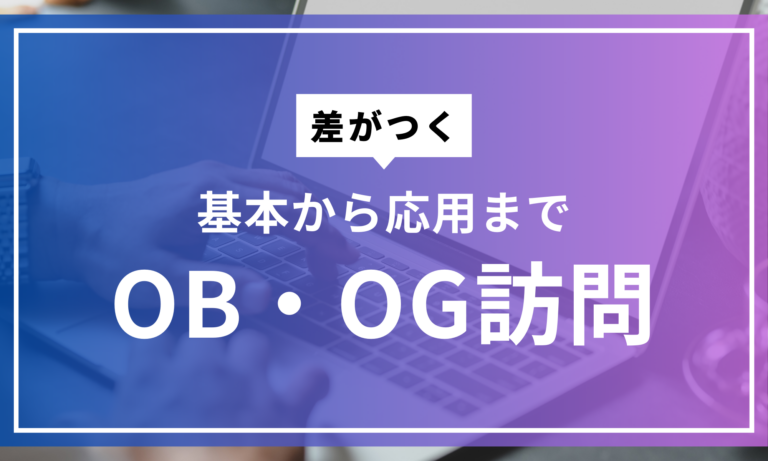はじめに
OB・OG訪問はなぜ重要?
OB・OG訪問は、企業のリアルな実情を知るための最も有効な手段の一つです。企業の公式サイトや採用ページには掲載されていない、実際の職場環境・社員の働き方・キャリアパスなどを直接聞くことができます。これにより、志望動機の説得力が増し、選考時のアピールポイントにもなります。
「やるかやらないか」で大きな差がつくポイント
OB・OG訪問をすることで、志望企業への理解が深まるだけでなく、面接での受け答えにも差が出ます。また、訪問を通じて企業の求める人物像を把握し、それに沿った自己PRを構築できるため、結果として内定率を上げることができます。さらに、社員と直接つながることで、企業側に名前を覚えてもらい、選考で有利になる可能性もあります。
本記事のゴール
本記事では、OB・OG訪問の基本から応用までを詳しく解説し、就活生がすぐに実践できるよう具体的なステップを紹介しています。読み終えたときには、「誰に」「どうやって」OB・OG訪問を依頼し、「何を聞けばよいのか」が明確になり、自信を持って行動に移せるようになるはずです!
〈入門編〉OB・OG訪問の基本
OB・OG訪問は、企業研究を深め、就活を有利に進めるための強力な武器です。しかし、「そもそもOB・OG訪問とは何か?」「誰に、どのように依頼すればいいのか?」「訪問時に気をつけるマナーは?」といった疑問を持つ人も多いと思います。
この入門編では、OB・OG訪問が初めてでもスムーズに進められるように、OB・OG訪問の目的や基本的な流れ、適切な相手の探し方、依頼時のマナーや訪問時の注意点などを詳しく説明していきます。OB・OG訪問を最大限活用し、自分のキャリア選択に役立てるための基礎知識をつけましょう!
OB・OG訪問とは?
OB・OG訪問とは、就職活動をおこなう学生が、自分の大学の卒業生(OB・OG)や、興味のある業界・企業で働く社会人を訪ねて、仕事内容や職場の雰囲気などを直接聞くことです。企業の公式情報だけでは得られないリアルな声を知ることで、業界・企業研究を深めたり、自分に合ったキャリアを考える手助けになります。また、OB・OG訪問を通じて、就活の進め方や面接対策についてのアドバイスをもらえることもあります。
OB・OG訪問の最大の目的は、企業理解を深めることです。具体的には、以下のような情報を得ることができます。
- 企業文化や職場の雰囲気
- 実際の業務内容と働き方
- キャリアパス(昇進・異動・転職のしやすさなど)
- 求められるスキルや人材像
- 面接で聞かれる質問や選考対策
いつ・誰に・どうやって依頼する?
適切なタイミング
OB・OG訪問の最適なタイミングは、就活のフェーズによって異なります。業界・企業研究中(大学3年春~秋)は興味のある業界を明確にするため、エントリー・選考前(大学3年冬~4年春)は面接対策や志望動機のブラッシュアップに、選考後(内定承諾前)は最終的な意思決定の材料として活用すると効果的です。目的に応じて適切な時期に訪問することで、より有意義な情報を得ることができます。
| 就活フェーズ | 目安の時期 | 活用方法 |
| 業界・企業研究中 | 大学3年春~秋 | どの業界・企業に興味があるか明確にするために活用 |
| エントリー・選考前 | 大学3年冬~4年春 | 面接対策や志望動機のブラッシュアップに活用 |
| 選考後 | 内定承諾前 | 最終的な意思決定のために活用 |
OB・OG訪問の相手の探し方
OB・OG訪問を成功させるためには、まず適切な相手を見つけることが重要です。以下の方法を活用し、自分に合ったOB・OGを探しましょう。
大学のキャリアセンターを活用する
多くの大学のキャリアセンターでは、企業別の卒業生リストを保有しています。希望する業界や企業のOB・OGの連絡先を紹介してもらえることもあるため、まずは相談してみることをおすすめします。キャリアセンターに相談する際は、企業リストがあるかどうかを事前に確認し、具体的な業界や企業名を伝えるとスムーズです。また、相談の目的を明確にするために、あらかじめ質問を準備しておくと、より有意義なアドバイスを受けられます。
就活SNS・マッチングサービスを利用する
「Matcher」「ビズリーチ・キャンパス」などのサービスを活用すると、OB・OGとオンラインでつながることができます。これらのサービスでは、OB・OGが自己紹介や得意な相談内容を掲載しているため、自分に合った相手を選びやすいのが特徴です。利用する際は、プロフィールを充実させ、自己紹介を明確にすることで、相手に安心感を与えやすくなります。また、相談したいテーマを具体的に記載することで、相手にとっても有意義な面談になりやすく、より実りのある会話ができます。
企業の採用イベントを活用する
企業の説明会や座談会では、現役社員と直接つながるチャンスがあります。特に、少人数制の座談会では質問しやすく、個別の面談につながりやすいのが魅力です。事前に質問を考えておくことで、限られた時間の中でも効果的に情報を得ることができます。また、話を聞いて興味を持った社員には、後日連絡を取り、個別に話す機会を作ることで、より深い情報を得ることができます。
長期/短期インターンシップでネットワークを広げる
インターンシップでは、社員と直接交流できる機会が多くあります。メンターや座談会で知り合った社員に後日連絡を取り、OB・OG訪問の機会を作るのも有効です。インターン期間中に積極的に質問をし、良い関係を築いておくことで、後の連絡がスムーズになります。また、メールやSNSを活用して後日フォローアップを行うと、関係を継続しやすくなります。
LinkedInで検索・コンタクトを取る
LinkedInを利用すると、企業の社員のキャリアや経歴を確認しながらメッセージを送ることができます。特に、共通の大学出身者や興味のある職種の社員を探しやすいのが特徴です。「大学名+企業名」で検索すると、OB・OGを見つけやすくなります。メッセージを送る際は、簡潔に自己紹介し、具体的な質問を添えることで、相手の負担を減らしつつ、スムーズに会話を進めることができます。
OB・OGがいない場合の対処法
OB・OGが見つからない場合でも、企業の情報を得る方法は他にもあります。以下の対策を試して、情報収集の手段を広げましょう。
企業に直接問い合わせる
企業の採用担当者やインターンシップ担当者に直接連絡し、社員との面談を依頼する方法もあります。企業の公式HPに「お問い合わせ」や「採用情報」ページがある場合、そこから問い合わせが可能です。問い合わせをする際は、簡単に自己紹介をし、面談を希望する理由を明確に伝えることが大切です。採用担当者に直接メールを送る場合は、適切なマナーを守りましょう。件名を分かりやすくし、宛名を正しく書くことで、相手にとって分かりやすいメールになります。また、本文は簡潔かつ明確にし、敬意を持った表現(例:「ご教示ください」「大変興味を持っております」など)を使うと、丁寧な印象を与えられます。
SNSを活用して情報収集する
X、Instagram、LinkedInなどのSNSでは、企業の社員が仕事に関する情報を発信していることがあります。特に、noteやキャリア系YouTubeでは、働く環境やキャリアのリアルな話を聞くことができます。企業名や職種で検索すると、情報発信をしている社員を見つけやすくなります。また、コメントやDMで質問をする際は、失礼のないように注意し、簡潔かつ丁寧なメッセージを心がけることが大切です。
大学のキャリアセンターや教授に相談する
キャリアセンターだけでなく、ゼミの教授や研究室の先輩に相談するのもひとつの方法です。過去に同じ業界を志望した卒業生を知っている場合があるため、具体的な希望業界や職種を伝えたうえで相談すると、適切なアドバイスや紹介を受けられる可能性があります。紹介してもらった場合は、必ずお礼を伝えることで、良好な関係を築くことができます。
企業の説明会やイベントに参加する
OB・OG訪問の代わりに、企業の説明会や座談会で直接社員と話す機会を増やすのも有効です。特に、オンライン説明会では、地方在住でも気軽に参加できるメリットがあります。事前に質問を考えておくと、限られた時間の中でより充実した情報を得ることができます。また、興味を持った社員と後日コンタクトを取り、個別で話す機会を作ることで、さらに深い企業理解につなげることができます。
依頼時のマナーと依頼メール例文
OB・OG訪問を成功させるためには、最初の依頼の仕方が重要です。マナーを守り、分かりやすく簡潔なメールを送りましょう。この章では、依頼時の基本マナーや、実際に使えるメールの例文を紹介します。
【基本マナー】
- 件名は簡潔に記す
例)「OB・OG訪問のお願い(〇〇大学 氏名)」
- 本文は「自己紹介 → 目的 → 面談のお願い」の流れで構成する
- 返信しやすいように候補日を複数提示する
- SNSではいきなり長文を送らず、短く要点を伝える
例)「はじめまして。〇〇大学の〇〇と申します。突然のご連絡失礼いたします。△△業界に興味があり、就活の参考にお話を伺えたらと思っています。もし可能でしたら、30分ほどお時間をいただけませんでしょうか?」
例文:
件名:OB・OG訪問のお願い(〇〇大学 氏名)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様
突然のご連絡、失礼いたします。
私は〇〇大学〇〇学部〇〇学科に在籍しております、〇〇(氏名)と申します。
このたび、貴社の△△事業に大変興味を持ち、業界研究・企業理解を深めるためにOG訪問をさせていただきたく、ご連絡を差し上げました。
私は現在、△△業界に関心を持ち、就職活動を進めております。特に貴社の△△という取り組みに魅力を感じており、実際の業務内容やキャリアパスについて、直接お話を伺えればと考えております。
お忙しいところ大変恐縮ですが、もしお時間をいただけるようでしたら、以下の候補日時でご調整可能な日時はございますでしょうか。
もちろん、ご都合に合わせて調整させていただくことも可能です。
【候補日時】
・〇月〇日(〇)〇時〜〇時
・〇月〇日(〇)〇時〜〇時
※オンライン・対面どちらでもご都合の良い方法でお願いできますと幸いです。
突然のお願いで恐縮ですが、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
お忙しいところお手数をおかけしますが、ご返信いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------
〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科
〇〇〇〇(氏名)
メール:〇〇@〇〇.com
--------------------
訪問時の基本マナー
挨拶・服装・持ち物
OB・OG訪問は、企業の方と直接お会いする貴重な機会であり、就職活動の一環としても重要な場面です。社会人としての基本的なマナーを守ることで、相手に好印象を与え、スムーズなやり取りができるようになります。
挨拶
初対面の方に対しては、明るくはっきりとした声で自己紹介をすることが大切です。訪問時には「本日はお時間をいただきありがとうございます。〇〇大学〇〇学部の〇〇と申します。」と名乗り、感謝の気持ちを伝えましょう。また、面談が終わる際にも「お忙しいところ、貴重なお時間をいただきありがとうございました。」と改めてお礼を述べることで、礼儀正しさを印象付けることができます。
服装
服装は訪問する場所や企業の雰囲気に合わせて選びましょう。企業のオフィスを訪れる場合は、リクルートスーツやビジネスカジュアルを選ぶのが無難です。スーツを着用する場合は、シワや汚れがないように注意し、清潔感を意識することが大切です。「カジュアルな服装で構いません」と言われた場合でも、だらしない印象を与えないよう、シャツにジャケットを合わせるなど、シンプルで清潔感のある服装を心がけましょう。
持ち物
当日は、スムーズに話を進められるように必要な持ち物を準備しておきましょう。まず、メモを取るためのノートとペンは必須です。スマートフォンでメモを取ることも可能ですが、場合によっては失礼にあたることがあるため、ノートを持参するのが安心です。また、事前に準備した質問リストを持っていけば、聞きたいことを漏らさずに済みます。企業研究シートや、もし持っていれば名刺を用意するのも良いでしょう。さらに、訪問先のカフェなどでの支払いが発生する可能性があるため、交通費や飲み物代も忘れずに持参してください。
時間管理
訪問時間の目安
OB・OG訪問の面談時間は、一般的に30〜60分程度が目安となります。訪問前に相手のスケジュールを確認し、時間を超えないよう意識しましょう。特に企業のオフィスで訪問をする場合、終了時間が近づいたら「本日は貴重なお話をありがとうございました。お時間が過ぎてしまいましたが、大丈夫でしょうか?」と確認すると、丁寧な印象を与えられます。
また、やむを得ず遅刻する場合は、必ず事前に連絡を入れ、「〇分ほど遅れてしまいそうです。誠に申し訳ございません。」と謝罪の意を伝えましょう。可能であれば、訪問先の都合に合わせて別の日程に調整する提案をするのも良い方法です。さらに、もし訪問をキャンセルしなければならなくなった場合は、できるだけ早く連絡をし、謝罪とともに代替日程を提案することが重要です。直前のキャンセルは相手に迷惑をかけるため、慎重に対応するよう心がけましょう。
〈実践編〉OB・OG訪問を有意義にするための準備
OB・OG訪問は、ただ話を聞くだけではなく、自分の就職活動に役立つ具体的な情報を得る場です。そのためには、事前の準備が欠かせません。この章では、訪問をより有意義なものにするために、効果的な質問リストの作り方や、事前リサーチのポイントを紹介します。適切な質問を用意することで、業界や企業のリアルな実態を知ることができ、また、相手に対しても好印象を与えることができます。さらに、企業研究の進め方についても解説し、訪問前にどのような情報を集めておくべきかを明確にします。しっかりと準備を整え、実りのある訪問にしましょう。
質問リストの作り方
OB・OG訪問では、限られた時間の中で自分にとって有益な情報を得ることが重要です。そのためには、相手の経験や視点を引き出しながら、業界や企業の実態を理解できるような質問をすることが求められます。
おすすめ質問
「この業界・企業を選んだ決め手は何ですか?」
この質問をすることで、相手が業界や企業を選んだ理由を知ることができます。特に、入社前にどのような視点で企業を比較したのか、決め手となったポイントは何だったのかを聞くことで、自分の就職活動の軸を考える際の参考になります。また、「〇〇という点が決め手になったが、実際に働いてみてどう感じていますか?」といった追加質問をすることで、よりリアルな意見を引き出すこともできます。
「入社前と入社後のギャップはありますか?」
入社前に抱いていたイメージと、実際に働いてみて感じた現実の違いを知ることで、理想と現実の差を理解することができます。求人情報や会社説明会だけでは分からない、働く中での発見や意外な一面を聞くことができるため、より具体的にその企業での仕事をイメージしやすくなります。また、ギャップを感じた部分をどのように乗り越えたのかを聞くことで、自分が将来直面するかもしれない課題に備えることができます。
「一日の仕事の流れを教えてください。」
実際の業務内容や働き方のイメージをつかむ際に有効な質問です。具体的にどのような業務を担当し、どのような時間の使い方をしているのかを知ることで、詳細にイメージできるだけでなく、自分の働き方の理想と合致しているかを判断する手がかりになります。また、部署や職種によって働き方が異なる場合もあるため、「〇〇部ではどうですか?」といった形で、より詳しく掘り下げるのも有効です。
「どのような人が活躍していますか?」
企業が求める人物像や、社内で評価されやすい人の特徴を知ることができる質問です。この質問をすることで、その企業で求められるスキルや姿勢が明確になり、自分に合った環境かどうかを判断しやすくなります。また、付随して、「そのような人になるためには、入社前にどのような準備をしておくと良いですか?」と聞くことで、就活の準備に役立つアドバイスをもらえる可能性もあります。
「仕事のやりがいと大変な点を教えてください。」
仕事の魅力だけでなく、実際に働く中で感じる難しさについても知ることで、よりバランスの取れた企業理解ができます。やりがいについての話を聞けば、自分がその仕事を楽しめるかどうかのヒントが得られますし、大変な点についての話を伺うことで、入社後に直面する可能性のある課題を知ることができます。また、「どのようにして大変なことを乗り越えていますか?」と尋ねることで、その企業ならではのサポート体制や職場の雰囲気についても知ることができます。
NG質問
「給料はどのくらいですか?」
給与は働く上で重要な要素ですが、OB・OG訪問の場で率直に聞くと、「待遇面にしか関心がない」「志望動機が薄い」と思われてしまう可能性があります。特に、訪問相手が人事ではなく現場の社員の場合、自分の給与を具体的に話しにくいと感じる人もいます。
おすすめの聞き方
「この業界全体の給与水準はどのような傾向がありますか?」
「若手社員のキャリア形成の中で、評価や昇給のポイントになるのはどんな部分ですか?」
こうした質問にすることで、給与に関する情報を間接的に得られるだけでなく、どのような努力が評価されるのか、長期的なキャリアプランを考える上でのヒントも得られます。
「会社の良くない点は何ですか?」
企業のデメリットを知ることは大切ですが、ストレートに「良くない点は?」と聞くと、ネガティブな印象を与えたり、答えづらいと感じさせてしまう可能性があります。企業の悪口を引き出すような質問は失礼にあたるため、聞き方に工夫が必要です。
おすすめの聞き方
「この仕事をする中で、大変だと感じるのはどのような点ですか?」
「入社前に知っておいたほうが良い、業界・企業の特徴はありますか?」
このように言い換えることで、企業の課題や大変な部分についても聞きやすくなります。また、デメリットに対してどう向き合っているのかを聞くことで、実際の働き方や職場の雰囲気をより深く理解することができます。
「御社の選考で有利になる方法を教えてください。」
この質問は、「ズルをして選考を突破したい」という印象を与えかねません。また、企業ごとに明確な「有利になる方法」があるわけではなく、社員によっては答えにくいと感じる可能性もあります。
おすすめの聞き方
「どのような人物が選考を通過しやすいと感じますか?」
「求められる資質や、面接で重視されるポイントについて教えていただけますか?」
こうした聞き方なら、選考の評価基準や企業が求める人物像を知ることができ、自分がその企業に合っているかを考える材料にもなります。
「印象に残る質問」をするコツ
OB・OG訪問では、相手の記憶に残るような質問をすることで、より深い話を引き出し、有意義な時間にすることができます。そのためには、一般的な質問にとどまらず、相手の経験に基づいた質問をすることが重要です。たとえば、「〇〇さんが入社して一番成長を実感した瞬間はいつでしたか?」と尋ねることで、具体的なエピソードを通じて、仕事のやりがいや成長の機会について詳しく知ることができます。
また、企業研究を事前に行い、それを踏まえた具体的な質問をすることも効果的です。たとえば、「〇〇の事業戦略について、社員の立場から見た展望を伺えますか?」といった質問は、相手にとっても答えやすく、会社の方向性やビジョンを深く理解する助けになります。
ポイントは、「答えやすさ」と「相手の経験を引き出すこと」を意識することです。そうすることで、表面的な情報ではなく、実際の働き方や職場のリアルな雰囲気を知ることができ、より有益な学びにつながるでしょう。
事前にリサーチすべきポイント
OB・OG訪問を有意義なものにするためには、事前のリサーチが欠かせません。しっかりと情報を収集することで、より深い質問ができるようになり、表面的な内容ではなく、実際の働き方や企業のリアルな姿を知ることができます。
まず、企業の公式情報を確認することが基本です。企業のホームページでは、事業内容や経営理念、採用情報などが掲載されており、その企業が何を大切にしているのかを理解するのに役立ちます。また、ニュースリリースをチェックすることで、最近の動向や新規事業の展開など、企業の最新の取り組みを知ることができます。上場企業の場合は、IR情報を確認することで、経営方針や財務状況についての理解を深めることも可能です。
さらに、社員のインタビュー記事や口コミサイトを活用するのも有効です。企業の公式サイトや採用ページ、noteなどには、現役社員のインタビューが掲載されていることがあり、実際の仕事内容やキャリアの歩み方について具体的な話を知ることができます。加えて、OpenWorkやVorkers、就活会議といった口コミサイトでは、社員のリアルな声が投稿されており、企業の雰囲気や働き方の特徴を把握するのに役立ちます。ただし、口コミサイトの情報は個人の主観が強く反映されているため、鵜呑みにせず、複数の情報源を参考にしながら総合的に判断することが大切です。
このように、事前に企業について調べることで、OB・OG訪問時の質問の質が向上し、より深く有意義な話を聞くことができるようになります。
【企業研究シートの作成例】
OB・OG訪問を有意義なものにするためには、事前に企業について深く理解しておくことが欠かせません。その際に役立つのが「企業研究シート」です。企業研究シートとは、訪問する企業の基本情報や特徴、自分の志望理由との関連性などを整理した資料のことで、事前準備の一環として活用できます。
このシートを作成する目的は、大きく分けて二つあります。一つは、企業の事業内容や強み、業界内での立ち位置などを体系的に整理し、自分の理解を深めることです。公式サイトやニュースリリース、社員インタビューなどの情報を集めてまとめることで、企業の特徴を把握しやすくなります。もう一つの目的は、OB・OG訪問時に効果的な質問をするための準備をすることです。事前に企業研究を行い、自分の関心や疑問点を明確にしておくことで、的確で深みのある質問ができ、より実りのある対話につなげることができます。
企業研究シートには、企業名や業界、事業内容、競争優位性などの基本情報に加え、最新のニュースや経営戦略、さらには自分の志望理由との関連性などを記載します。たとえば、企業の新規事業や海外展開の動向を調べておけば、「現在の戦略について社員の立場からどのように感じていますか?」といった、より具体的な質問を考えることができます。
項目 内容 企業名 〇〇株式会社 業界 IT・メーカー・金融など 事業内容 主力商品・サービス 強み・特徴 他社と比較した際の強み、競争優位性 最新ニュース M&A、海外展開、新規事業など 志望理由との関連 どの点に魅力を感じるか
〈差をつける編〉OB・OG訪問を成功に導く応用テクニック
OB・OG訪問は、単に企業の情報を集める場ではなく、企業や働く人との関係を深め、自分自身の就活を一歩前に進める貴重な機会です。しかし、ただ話を聞くだけで終わってしまうと、得られる情報も限られ、他の就活生と差をつけることが難しくなります。この章では、OB・OG訪問をより有意義なものにするための応用テクニックを紹介します。これらを実践することで、単なる情報収集にとどまらず、自分の考えを深め、企業とのつながりを強化し、最終的に選考の場でより説得力のある志望動機や自己PRを伝えることができるようになります。
🌟あわせて読みたい🌟
他の就活生と差をつけるためのポイント
自分の意見を伝える重要性
OB・OG訪問において、単に相手の話を聞くだけで終わらせるのではなく、自分の意見をしっかりと伝えることが重要です。企業の先輩方は、学生がどのように会社を捉えているのか、またどのような考えや価値観を持っているのかに関心を持っていることが多いため、一方的に話を聞くだけではなく、自分の考えを交えながら会話を進めることが大切になってきます。
具体的な方法としては、まず相手の話を聞いたうえで、「それは〇〇ということですか?」と確認しながら、相手の意図を正しく理解しつつ会話を深めることが効果的です。また、「私は〇〇な考えを持っているのですが、実際の現場ではどうですか?」と、自分の意見を交えて質問することで、より具体的なフィードバックを得ることができます。さらに、「今後のキャリアを考える上で〇〇を大事にしたいと考えているのですが、御社ではそれを実現できますか?」と、自分の価値観と企業の環境を照らし合わせながら質問することで、より実践的な情報を得ることができるでしょう。
このように、単なる情報収集ではなく、自分の考えを伝えながら対話を進めることで、相手にも印象を残しやすくなり、他の就活生と差をつけることができます。
フォローアップの極意
OB・OG訪問が終わった後は、感謝の気持ちを伝え、学びを深めるためのフォローを行うことが大切です。まず、訪問後24時間以内にお礼のメールを送るのがマナーとされています。単なる形式的な挨拶ではなく、具体的な学びや感謝の気持ちを伝えることで、より良い印象を残すことができます。お礼メールの具体的な書き方については、記事「【差がつく】OB/OG訪問お礼メールの極意|例文&実践テクニック完全版」に詳しく解説されていますので、参考にしてみてください。
また、訪問中に聞きそびれたことや、より深く知りたい点があれば、追加の質問をするのも有効です。たとえば、「お話しいただいた〇〇についてもう少し詳しく知りたいのですが、関連する資料などございますか?」といった形で簡潔に質問すると、相手の負担を減らしながら、具体的な情報を得ることができます。
さらに、話し足りなかった場合や、より詳しく伺いたいことがある場合は、次回のアポイントを取ることも検討しましょう。「引き続きお話を伺いたいのですが、再度お時間をいただくことは可能でしょうか?」と丁寧に依頼することで、継続的な関係を築くことができます。こうしたフォローをしっかり行うことで、OB・OG訪問をより実りあるものにすることができるでしょう。
複数のOB・OG訪問をつなげる方法
OB・OG訪問をより効果的なものにするためには、単発の「点」ではなく、連続性を持たせた「線」としてつなげていく意識が重要です。一人の社員と話をする機会を得たら、そのつながりを活かし、次の訪問へと発展させることで、より多角的な視点を得られ、企業理解を深めることができます。
たとえば、特定の部署の方から話を伺った際に、「他の部署の方や、より詳しくお話を聞ける方をご紹介いただけませんか?」と尋ねることで、社内の異なる視点を知る機会が生まれます。また、企業説明会や交流イベントにも積極的に参加することで、さらなる人脈を築くことができます。
さらに、効率的にOB・OG訪問を重ねたい場合は、BaseMeのようなスカウト型新卒採用プラットフォームを活用するのも有効です。BaseMeには、高い行動力やビジョンを持つ学生が多く登録しており、AIが個々の価値観や強みを解析し、最適な企業とのマッチングを支援します。これにより、企業選びの選択肢が広がるだけでなく、自分に合った企業との接点を見つけるきっかけにもなります。
また、LinkedInやMatcherなどのサービスを活用し、訪問した社員のネットワークをたどるのも効果的です。特にBaseMeを利用している学生は、ハイレベルな就活生が多く、積極的にOB・OG訪問を行っているため、コミュニティ内のつながりを活かしてさらに多くの社員とコンタクトを取ることも可能です。
このように、一度の訪問で終わらせず、次へとつなげる意識を持つことで、企業理解を深めるだけでなく、内定獲得の可能性も高まります。BaseMeのようなキャリア支援プラットフォームを活用しながら、自分のネットワークを最大限に広げ、納得のいく就職活動を進めていきましょう。
選考対策としての活用法
訪問内容を選考に活かす方法
OB・OG訪問で得た情報は、選考の際にしっかり活用することで、より説得力のある志望動機や回答を作ることができます。特に、志望動機に「具体性を持たせる」ことが重要です。単に「企業の雰囲気が良いと思った」ではなく、実際に社員と話した経験を交えながら、自分がなぜその企業に魅力を感じたのかを明確に伝えましょう。訪問を通じて得たリアルな感想を加えると、より具体的で納得感のある志望動機になります。
例)「実際に社員の方とお話しして、〇〇の社風が自分に合っていると感じました。」
また、面接での回答を強化する際にも、OB・OG訪問での学びを活かせます。企業の価値観や文化を、実際のエピソードを交えて説明することで、表面的な理解ではなく、深く共感していることを伝えられます。
例)「OBの方からお伺いした△△なエピソードが、貴社の〇〇な価値観を象徴していると感じました。」
実際の選考でOB・OG訪問の経験を活かしたエピソードを話す例
OB・OG訪問で得た情報や気づきを志望動機や自己PRに組み込むことで、説得力のあるエピソードを語ることができます。ただ訪問した事実を伝えるのではなく、どのような学びがあり、自分の考えや行動にどのような変化をもたらしたのかを具体的に説明することが重要です。
例)「〇〇様のお話を聞いて、△△な価値観が社内に根付いていることを実感し、より志望度が高まりました。」
例)「訪問時に〇〇様からいただいたアドバイスをもとに、自己分析を深め、自分が大事にしたい軸を明確にしました。」
まとめ:OB・OG訪問を就活の武器にしよう!
本記事の重要ポイントおさらい
OB・OG訪問は、情報収集だけを目的にするのではなく、自分の意見を伝え、次につなげることが大切です。訪問中は積極的に質問をし、自分の考えを交えながら会話を深めることで、より有意義な時間にすることができます。
また、訪問後のフォローアップも欠かせません。お礼のメールを送るだけでなく、追加の質問をしたり、必要に応じて次回のアポイントを取ったりすることで、より深い情報を得られる可能性が高まります。
そして、訪問で得た情報は選考の場面で活かしましょう!社員との会話をもとに志望動機に具体性を持たせたり、面接での回答を強化したりすることで、企業への理解度や熱意をより効果的にアピールできます。
一度の訪問で終わらせず、他のOB・OG訪問につなげることも重要です。紹介を依頼したり、座談会や交流イベントに参加したりすることで、より多角的な視点から企業を知る機会を増やせます。
このように、OB・OG訪問を最大限に活用することで、就職活動そのものをより充実したものにすることができます。
今すぐやるべきアクションリスト
| 企業研究をおこない、訪問したいOB・OGをリストアップする |
| OB・OG訪問のアポイントを取り、日程を調整する |
| 訪問時に聞く質問を準備する |
| 訪問後にお礼メールを送り、追加の質問をする |
| 次回の訪問につなげるためのアクションを考える |
OB・OG訪問は、就活の成功に直結する重要なステップです。しっかり準備し、マナーを守りながら行動することで、他の就活生と差をつけましょう!
\就活を自分らしく進めるなら!/